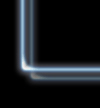Peaceful Days -14 Peaceful Days -14
祭りの次の日は休みになっていて、そのまま週末と組み合わせて連休に入った。
済んだ秋晴れは長続きするようで、気持ちの良い天気はしばらく続いてくれそうだ。
朝起きて、京は昨日までの慌ただしいものとは打って変わった静かな時の流れをゆったりと感じながら、雪塚の作ってくれた食事を取った。
明後日退院する母親の話をしながら、勝也の家に行ってみようかと考えたのは、ふとした思い付きだった。
「お出かけに?」
「うん、勝也のところに行こうかと思って」
「初めてですよねぇ」
珍しいと少し目を見開いた雪塚だったが、自分から友人の家へ行くことを決めた京を喜び、とても嬉しそうな顔をしてくれた。
雪塚は、京と姉のもう一人の母と言ってもいい人だ。体の弱い母の代わりに京たちの面倒をよく見てくれ、育ててくれた。母方の実家と深い繋がりのあった人らしいが、あまり詳しい事は知らされていない。解っているのは、若い頃に未亡人になった事と、二人の息子が居る事。そして子供たちが無事独立し、手が離れてからは、月乃家にとても尽くしてくれているということ。
複雑な事情を抱える家族の中で、姉弟を我が子のように可愛がり、叱り、躾け、喜び、笑い、そして苦しい時も当然のように一緒に過ごしてくれた。この人が居てくれなければ、自分たちの家族はとっくの昔に崩壊していたかもしれない。そう思った事は一度や二度ではなかった。
けれど、それ以上の恩を自分は貰っているのだと、雪塚は笑う。母よりもふた廻りは年上の女性だが、やはり自分たちにとっては、母親と同じような存在だった。
「いってらっしゃい」
玄関先でちょっとした菓子を持たされ、優しい笑顔に見送られる。数日後には、この風景に母親の姿が戻るのだと思うと、心の中の温かさは更に膨れ上がった。
ひやりとした、秋特有の風の冷たさが気持ち良い。
住所と大凡の場所しか知らない友人の家へ足を進める。特に約束はしていないので、勝也が家にいるかも解らなかったが、居なくても別に構わないと思った。いつもと立場が逆になるだけだ。
涼やかな空気の中、金木犀の薫りが漂ってくる。静かに深く呼吸をしながら歩いていると、目の前の角から、背の高い人影がひょいと現れた。
「お、京??」
「あれ? 勝也?」
「今からお前の家行こうと思ってた」
「そうなんだ」
同じ事を、同じタイミングで考えていたのかと思うと、なんだかとても面白くて、京はふふ……と笑った。
「珍しいな」
京の外出を言っているのだろうと解る。
「うん……、雪さんにも言われた」
「もしかして、俺んち来るつもりだった?」
尋ねるように聞かれ、言い当てられたせいか、何故か急に恥ずかしいような気持ちになりながら、コクンと頷いた。
「そかそか」
嬉しそうな声音と共に、ぽんぽんと大きな手が京の頭を撫でる。
「そういや、昨日の先輩たち、これやって盛り上がってたなー。ずっとやってみたかったんだって。喜んでたよ」
「これ?」
肯定の意味なのか、また頭の上に暖かな勝也の手が乗る。
「……ふーん……?」
こんな事になんの意味があるのだろだろうか。良く解らなくて首を傾げると、勝也は悪いことじゃないから気にするなと笑った。
「立ち話もなんだな。折角京が俺の家に来てくれる気になったんだし、ウチ行こうか。それとも天気もいいし、そこの公園でもいく?」
勝也は、今通ってきただろう道を引き返しながら話しかけてくる。
京としては、勝也と二人きりで話せれば場所は何処でもよかったので、どちらでも構わないと答えた。
「じゃぁ、のんびり寄り道の散歩しながら、家にいこっか」
勝也の提案に、京は頷いた。
道すがら、勝也が話してくれた話に、京は驚きを隠せなかった。
「親子?」
はっきりした名前などは伏せられて出てこないが、どう考えても英語教諭の佐々木の事と、昨日京に乱暴をした他校生の一人を指しているのは明らかだった。だからこそどう返事をしてよいか戸惑う。
「大人気ないよなぁ……」
呆れたような響きが印象的だった。
「息子を入学させるために、長年色々準備していたんだろうけど、結果的に上手く行かなかった。で、家では息子に当たり、授業では京に……。そしてあの結末」
大きな溜め息。
「……」
公園の石畳を一つ一つ目で追い、ゆっくりと歩きながら、京はあまり整理されていない断片的な自分の記憶を辿ってゆく。
誰のせいにも出来ない。そう解っていても、何かに対してぶつけなければ、耐えられない人もいるのだ。事実、京はその対象になった。
弱い人間。そういってしまえば簡単だが、間違うことなく自分はそちら側に属する人間で、京の中ではなかなか答えの出ない問題だ。
そして、目の前の現実として、佐々木はそれなりのリスクを負う事になるだろう。
「色々……上手く行かないね」
ぽつりと言うと、勝也は「世の中の大半はそんなもんだけどな」と、やけに大人びた感想を呟いた。
「だからって、自分の不運を、誰かのせいにしたりするのは間違ってると思うぞ」
確かにそうだ、と京も同意しながら小さく笑った。
「ところで、京はなんでまた俺の家に来る気になったんだ?」
「……ん? あぁ、母さんが明後日……」
母親の退院の話から切り出し、そして間近に控えた渡米の事を言葉少なに伝えた。
「また、ずいぶん急な……って言ってもいい? ……結構驚いた」
「ごめん。なかなか伝える時間が無くて」
「まー、祭りだなんだと忙しかったもんなあ」
「ん……」
「で、どのくらいあっちに行く事になるんだ?」
「さぁ……」
予定では一年だが、母親の病状次第というのが本当の所だ。快方への希望を持って行くことには間違いないが、最悪の事態への覚悟は、家族全員口に出さずとも心の隅に抱いている。そうなれば、京にとって日本という国へ戻る事も、それほど重要な問題では無くなってしまうかもしれない。
「もしかしたら、そのままかも」
「…………そうか」
別れを惜しんでくれているのだろう、気遣いが伝わってくる。
「まぁ、京とは距離が遠くなっても、あんま関係なさそうだけどな。今はネットもあるから連絡取り放題だし」
このまま変わらず友人で居ようと言ってくれる、勝也の優しさが嬉しい。
微笑みに緩む慣れない目元が、自分の顔だと解っていても、とても不思議で新鮮に感じた。
「もうちょいで、家につくよ」
指差された先には、綺麗に切りそろえられた生垣がみえた。
「あの白い?」
「そうそう」
初めて見た勝也の家は、品の良い作りの二階建ての家屋で、程よく手入れされた庭には綺麗な花が咲いていた。
「勝也の家っぽい……」
「そうか? 全体的に母さんの好みだけどな」
手馴れた様子で門を開き、招き入れるように京を促してくれる。
家族の気配は感じなかったが、とりあえず「こんにちは」と小さく挨拶し、そのまま玄関を潜る。勝也の部屋があるという二階への階段を上ろうとしたその時だった。
ふわりと、とても馴染みのある、そしてひどく懐かしく、むしろ恋しいと名付けたい、あの風が通り過ぎた。
思わず足を止め、目を瞑った。
足元から、打寄せる波のヴィジョンが広がってゆく。
幻と解っていて、心臓が一つ、強く鳴る。
「あ、タクちゃん」
何事も無いような友人の声が傍から聞こえた。
「なんだ、出かけたと思ったら、もう帰って来たのか?」
他愛のない家族の会話だった。
なのに、これは……。
この感覚はなんだろう。
「タクちゃんこそ、まだ出かけてなかったの?」
「今から出る」
そっけない程、抑揚の無い声。
なのに、どうしてこの人の声は、こんなにも深く心の中へと沁みこんで来るのだろうか。
思わず振り返る。吸い込まれそうな琥珀色の瞳と、一瞬目が合ったような気がした。
時にすれば僅か一秒も無いだろう。なのに、京の周りには、もう長い間潜っていないはずの、あの海の感覚が満ち溢れ、優しくたゆたいはじめる。
「あ、そうだ。俺の友達の京」
突然、紹介された事に気がつき、反射のように頭を下げた。声は出なかった。
現実ではない海の風景。こんなのはおかしいと、頭では解っている。けれど、内側からあふれ出て来る、この名前も知らない熱い何かを止める術を京は知らない。
「ごゆっくり」
こちらに興味を示さない後姿から、京へと向けられた一言。短い声が京の耳元に届き、そして消えてゆく。
「いってらっしゃーい」
気安い勝也の声に見送られ、その人はドアの向こうへと消えていった。
残されたのは、彼の人の残した微かな海の余韻。
一体どうしてしまったのだろう。胸が痛い。
締め付けられるように、痛い。
でもそれは、決して辛いものではなく、深い深い夜の海に包み込まれる安堵に、とても良く似ていて……。
「今の兄貴でさ……ってあれ? 京??」
勝也が慌てたように京の名前を叫んだ。
「京?!」
顔を覗きこまれ、あまりの近さに驚く。
「え?」
「おい……?! どうしたんだ? どこかぶつけた? 痛いのか? 具合悪い?」
「え……?」
慌てる勝也の指先が頬に触れ、濡れた感覚を広げる。
「泣いてる、泣いてる。うわ、どうしよう」
「え? え?」
自分で顔をグイと拭って驚いた。
「あれ、なんだこれ。泣いてるの俺? なんで??」
「こっちが聞きたいよ!!」
珍しいくらい慌てている勝也を目の前にして、京も自分の事が解らずうろたえた。
あの事故以来、人前では勿論、一人の時も泣けなかったのに。
唯一海の中だけで覚え、感じる事が出来た、この濡れた感触。
どうして? そう思った瞬間、さっきすれ違った人を思い出す。
途端、再び大量の涙が零れてきた。
「京! わわわ……」
ティッシュを箱ごと手渡され、別の箱から大量に引き抜かれたティッシュの山が京の顔の上に乗せられる。
「勝也、俺どうしたんだろ……」
「解らないよ! こっちが聞きたいくらいだし!」
慌ててどこからか取ってきたタオルを差し出されたが、受け取るより先に顔を拭われた。
「俺も解らない……」
本当に解らないのだと、涙が止まらないまま背の高い友人を見上げると、心底困ったような顔をしながらも、大きな手で優しく頭を撫でてくれた。

その人とは、一瞬すれ違っただけだった。
ふわりと過ぎる、優しい風。
あの深い夜の海と同じ気配を持つ人。
――出来るなら、もう一度で良いから……、逢いたいと思った。あの人に。
自分の中に生まれた名前も知らない一つの感情を、そっと大事に心の奥に仕舞い込む。
そして。
京は、生まれて初めて”帰りたい"という希望を自ら抱き、優しい友人と穏やかに過ごすであろう日々を思い描いた。

そして、一年と数ヵ月後。
帰国した京の背が、見違えるほど高くなり周囲をとても驚かせたのは、また別の話……。
END
BACK | INDEX


|


 Peaceful Days -14
Peaceful Days -14