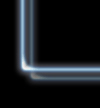Peaceful Days -12 Peaceful Days -12
後日に入った祭りは、そのまま後夜祭へと続く。
中学という思春期の難しい年頃の世代だが、元々育ちの良い子息の多い学校である。伝統と秩序を重んじる校風のお陰か、特に混乱も無く、順調且つ賑やかに時間は過ぎていった。
午後、京は学年の控え室になっている自分の教室に戻った。何か連絡事項が入っていないか確認していると、クラスメイトの一人が京を呼んだ。
「おーい月乃ー!」
声のした入り口を見ると、知った顔のクラスメイトの後ろに、病院にいるはずの母親の姿が見えた。
「え……?」
微笑み手を振る沙耶の隣には、少し心配そうな顔をした雪塚がいる。慌てて駆け寄ると、悪戯っぽく笑う母の顔があった。
「だ、大丈夫なの?」
「びっくりさせようと思って」
確かにとても驚いた。退院は数日後に控えてはいたが、だからといってこんな風に外出できる状態とは思っていなかったのだ。
「まだね、ちょっとしか居れないのよ……。でも、京がどんな風に学校で過ごしているか見てみたかったの。雪さんには迷惑かけてしまったけど、逢えて良かったわ」
本当に嬉しそうに笑う母を見て、京も付き添いで来てくれている雪塚も、強くは言えなくなり、苦笑するだけだ。
「とっても楽しそうね」
ふんわりとした優しい声で囁くように、沙耶の視線が周囲を見渡す。
「うん」
京は素直に頷いた。
「よかった」
細い指がそっと京の髪を撫で、小さく笑う。
微かに花の甘い香が漂った。病院の空気を纏わない、優しい母の匂いだ。
嬉しさが箍を外したのか、ほんの少し甘えたくなる気持ちを自覚する。珍しい感情に戸惑いながら、学校だからと、わざとそれに気がつかないふりをして、これからどうするのかを聞こうと口を開きかけた時だった。ふと周囲の空気に気がつく。
「……?」
何故か注目されている。不思議に思い首を傾げていると、沙耶がもう一度京の顔を見て微笑んだ。
「お邪魔しちゃったわね。京の顔も見れたし、そろそろ帰るわ」
「あ、……うん」
今もかなり無理をしてここまで来ているのだろう。隣で雪塚が不安そうにしている。
「今夜は少し遅くなるのよね? あまり無理しちゃダメよ」
自分の身体よりも息子を心配する母親の姿は、アメリカに居たときから変わっていない。
「うん、気をつける」
京にとっての本番は後夜祭だ。練習を一番頑張った日の時間くらいには遅くなるだろう。
「大丈夫。勝也が送ってくれるって」
考えてみれば、勝也も同じ年の同級生なのだから、送る送られるの話はおかしいのだが、勝也と京を見て、どちらが頼りになるかといえば一目瞭然。当然のように甘えてしまっている状態に、申し訳ない気分になるが、こればかりは仕方が無い。
それを聞いた母と雪塚は、安心したように頷くと、軽く周囲のクラスメイトに挨拶をして帰っていった。
二人の後姿を見送りながら、何気なく時計を見ると、リハーサルまであと十分という時間だった。とりあえず荷物を纏めようと振り返ると、慌てたように視線が散り、わざとらしい賑わいが湧き上がる。
「……?」
何かあったのだろうかと一瞬思ったが、リハーサルの前に勝也と待ち合わせをしていたことを思い出す。
京は慌ててバンドメンバーの控え室となっている音楽準備室へと向かった。
急いでいる事を理由に、京は一般の来場者が賑わう表の廊下を避け、校舎の裏にある庭を突き抜ける通路を選んだ。この道は目的地まで若干遠回りになるが、小柄な京が、来場者で混み合う場所を、無理に通るよりはマシなはずだ。
一般客以外は、特に立ち入りが規制されているわけではないので、裏方に廻っている生徒や、休憩している者など数人とすれ違う。時折、見知らぬ生徒に「後夜祭、楽しみにしているよ」などと声をかけられ少し戸惑いつつも会釈で返した。どこか不慣れな、それでいて決して嫌ではない不思議な感覚を持て余しながら。
庭の途中から長い渡り廊下に入り、旧講堂の横を過ぎようとしたその時だった。突然何か大きなものが視界を塞ぎ、京は危うくぶつかりそうになる。咄嗟にそれがドアだと気が付き、反射的に避けたが、何故か意図した方向とは逆へと強い力で引き込まれ、抵抗する術もなく、京は埃の舞う暗い部屋へと放り投げられてしまった。
「っ、……?」
コンクリートの床に強く肩を打ちつけ、痛みよりも息が詰まる。外の光に慣れた目が部屋の暗さに馴染まず、京は浅く喘ぎながら、役に立たない視線を左右にさ迷わせた。
高い天井に近い小さな窓から薄く届く光は、元々建物の影になっているのか寂しいほどか細く、部屋のほとんどが昼間とは思えぬ暗さに包まれている。
誰かが居る。
それも一人ではない。
ゾクリとした不安が背中を覆った。あの夢のような、どろりとした何かに引きずり込まれそうになる意識を必死で振り払う。
いつまでも転がっていては不利だ。懸命に気力を振り絞りながら、なんとか上体を起こし、無意識に打ち付けた肩を庇った。
それほど痛みはない。普通に動く。それを確認して少し安心し、同時にそれがあまり当てにならないことも思い出す。痛みという通常の感覚を失って、どのくらいたつのだろうかと。
転がってしまったせいで、ドアの位置が明確に解らない。逃げ道を把握しようと、慎重に辺りをうかがっていると、不意に誰かが笑う気配がした。
思わず後退る。数歩下がった所でガチャンと硬いものが背に当たり、何かが雪崩れのように横へスライドしながら倒れていった。音からそれがパイプ椅子だと解ったが、だからといって何の助けにもならない。ただ京の逃げ場を塞いだだけだ。
「月乃京」
突然、厭な響きの声にフルネームで呼ばれ、驚くよりも、嫌悪で眉間に皺が寄る。
いきなり顔にライトを当てられ、眩しさに目を顰める。
「うは、可愛い」
「マジでこれ?!」
別の下卑た声が愉快そうに甲高く笑う。
「ちょーっと痛い目遭わせて、泣かせればいいんだっけ?」
誰かに確認するような響き。しかしそれに返事はない。
不躾な光から開放されたが、乱暴な光陰に瞳孔の焦点がなかなかあわず、しかも逆光のせいで彼らの顔は見えなかった。
「二度と学校に来たくなくなるくらいが、ご希望なんだろ?」
「ついでに転校でもしてくれたら万々歳?」
「なぁ、どの程度苛めて良いかってのは……俺ら次第でいいんだよな」
彼らの言っている意味が解らなかった。
だが、身に迫った危機だけは着実に現実となってゆく。
「こんなちびっこ、二、三発引っ叩けばオワリじゃね?」
逃げようと身を捩ったが、グイと髪を掴まれ、強引に顔を上げさせられてしまう。
嫌だと暴れてみても、体格の差がありすぎて、ほとんど意味を成さなかった。こんな時にも役立たずな未熟すぎる自分の身体を恨むが、この体勢ではどうすることも出来ない。
「それじゃ、俺らが楽しくないでしょう」
「そそ、ママーって泣かれてオワリ」
「じゃぁ、ひん剥いちゃう?」
「いいねえ」
京は身を守るように制服の胸元を強く掴んだ。
「あはは、怖くて声もでねぇか」
ありきたりな台詞に酔っているのか、やたら嬉しそうな笑い声で数人が笑う。
「でもまぁ、いきなり叫ばれたら困るからな」
パンと乾いた音が頬の位置で鳴り、その衝撃で眩暈が起こる。無理矢理開かされた口の中へ、咽るほどの何かが突っ込まれ、その上から無造作にテープでふさがれてしまった。
「……!」
渾身の力を振り絞って暴れるが、何人居るのか解らない相手に子供の身体では、途方も無く無力だった。
「気が強ぇな、泣かねぇぞ」
「これからだろ?」
「早くエーンって泣いちゃった方が楽だぞ〜」
楽しげな声が耳元に聞こえた、その時だった。
「てめーらなにしてる!」
バン! という大きな響きと共に数人が雪崩れ込んでくる気配がした。
「大丈夫か!?」
庇うようにグイと腕を引きあげられ、フワリと身体が浮いた。そのままドアの際に立つ大きな黒い影に引き渡される。ドンという衝撃の割には柔らかく受け止められ、混乱したまま本能的にしがみついた。
「京、大丈夫か!?」
頭の上から降ってきたのは、聞きなれた勝也の声。丁寧に口に貼られたテープを剥がしてくれる。口に詰められていたものは何か布切れのようなものだった。
急に流れ込んでくる空気に噎せ返りながら喘いでいると、その間も薄暗い倉庫の中から数人が格闘するような音が聞こえてくる。
「ここは任せろ、お前は手ぇだすなよ」
「先輩に花もたせてや」
余裕とも楽しんでいるとも取れる響きだった。
「解っていますよ、でも忘れないでくださいね」
「大丈夫、怪我なんてさせねぇよ。そんなヘマするか」
「さすが先輩、……安心してお任せ出来ます」
なにが起こったのか解らないまま、自分を抱えてくれている背の高い友人を見上げる。光の加減か、今まで見たことも無いような、不敵な笑みを浮かべているように見えた。
逃げたほうが良い様な気もするのが、自分を抱えている勝也が動かないので判断に困る。どうすればいいのか、京はただ呆然と目の前の状況を見守るしか出来なかった。
「毎日僕がどんな目でパパに見られているか、お前に解るか!」
真っ先に捕まり、情けなく裏返った悲鳴で暴れていた少年が、突然叫んだ。それが半端な英語混じりだったと気付いたのは、微妙な一拍をおいてからだ。
何もかもが解らないので、とりあえず首を横に振ってみると、目の前の少年は、顔を真っ赤にして怒鳴り始めた。
「パパの言うとおりに、全部全部我慢してちゃんとしてきたのに、お前のせいで僕はこの学校に落ちた。でも、僕が落ちたのは実力が足りなかったからじゃない。足りなかったのは、絶対金だったってパパは言ってた。お前の親、幾らこの学校に積んだんだよ! 寄付金でこの学校に入れたからって偉いわけじゃないんだぞ!」
英語と日本語が混ざり合い、何を言っているのか解らない。いや、正しくは、言葉は解るが意味が理解出来なかった。
「寄付?」
「そうだ……お前ん家金持ちなんだってな。お前みたいなヤツでも、帰国子女なら金積めば、この学校に入れるんだ。啓明も落ちたもんだな」
馬鹿にしたような捨て台詞に、京は首を傾げた。
両親は学校に必要以上の金額を支払ったのだろうか。少し考えてみるが、それはあまり想像出来なかった。
確かにこの学校を選んだのは両親だったが、入るのは難しいかもしれないと最初から言われていたし、帰国子女枠とはいえ、京の場合は特殊なケースだったので、通常と同じ入学試験を受け、本決まりになるまで、面接は何度も繰り返された。
前例の無いケースに戸惑いながらも、誠意を見せてくれた面接官の教師たち。最後には申し訳ないとまで言われた、入学までのプロセスに、さらに金を積む理由があるだろうか。
「よく…解らない……」
「やっぱ、バカ? お前」
金属が擦れあうような、耳障りな嘲笑が響き渡る。しかしそれはどう見ても、負け惜しみにしか聞こえなかった
「あぁ、役者が揃ったみたいです」
突然勝也が抑揚も無く告げると、解った、と上級生たちも心得たように頷いた。
彼らの見事な立ち回りで、他校のものと解る制服を着た少年たちは、全て押さえつけられ、埃の舞い上がる床のうえで、成す術もなく無様に身悶えていた。
「何をしてるの!」
授業でよく聞く、甲高い声が遠くから響いてくる。神経質そうな声と歩き方。ギスギスに痩せた容姿は、性格そのものを現しているようで、晴天の下ではあまり見たくない姿だと、京は混乱する頭の片隅で妙にボンヤリと思った。
勝也はそっと京を庇うように立ち位置を変えながら、いかにも優等生然とした口調で口を開いた。
「月乃君が、他校の生徒に暴力を振るわれそうになっていました。先輩たちはそれを見つけて助けてくれたようです」
「またあなたたちなの!? 三池君の言っている事は本当??? まったく暴力は僕は嫌いな……」
不自然に佐々木の小言が止まる。
上級生たちが、小さく目配せを寄越した。
「とりあえず、月乃君が心配なので、保健室へ連れて行きます」
「……え、……ええ」
「では」
いいのだろうかと戸惑いながら振り返ると、すれ違い様、助けてくれた上級生の一人に、そっと耳打ちされる。
「これで借りは返したよん」
ふざけた調子でそういった人物の顔を、驚いてみつめ返した。
「あの時はごめんね」
別の上級生が、ごつい顔を不器用に歪め、少し照れたように笑う。
助けてくれたのは、夏の更衣室で京を襲った上級生たちだった。
BACK | NEXT
|


 Peaceful Days -12
Peaceful Days -12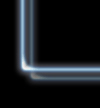



 Peaceful Days -12
Peaceful Days -12