 |
 |
|
 Peaceful Days -10 Peaceful Days -10
残暑も影を潜めたのか、夕方には涼しい風を感じるようになり、徐々に過ごしやすくなってきていた。  小高い丘の上にある、清和台総合病院。ここは京の母親の病気をずっと診ていてくれている、主治医が居る病院だ。京もあの事故からしばらく、入院していた事がある。 主治医の清田は五十代の穏やかな感じの人で、母の病の治療に関しては、日本で三本の指に入るという専門の医師だ。京の両親もこの主治医には全幅の信頼を寄せていて、難しいと言われていた今回の手術の執刀も、清田が担当してくれるというので踏み切った。 外来用の玄関から少し離れた、入院患者専用の入り口から入り、母親の病室へと向う。女性病棟らしい淡い桜色のドアをノックをすると、柔らかな声が返ってくる。そしてそのドアを開けてくれたのは父親だった。 「お、来たのか」 嬉しそうな父親の顔に、京はコクリと頷いた。 「お母さん退院できそうだって、雪さんから聞いたから」 「そうなの」 嬉しそうな母親の顔が、本当なのだと教えてくれる。よかった、と肩の力が抜けた。 「こら、まだ本当の退院じゃないんだから、無理はだめだぞ?」 「もう……解っているわよ」 「ならいいが」 息子を前にして、心配する父親の声がどこまでも甘く、なんだか当てられてしまいそうで、こちらが照れくさい。けれど、今気になる事を言わなかっただろうか。 「……完全な退院じゃない?」 「そうだ」 ゆっくりと息を吸い込みながら、父親が低く答えた。まるで自分に言い聞かせるような慎重な響きに、得もいえぬ不安が押し寄せてくる。 「……え?」 聞き返した声が震えていた。 一度聞いただけでは覚えられないような長い病名。手術の事例が非常に少なく、完治の可能性が極端に低い難病と言われる病。 「大丈夫。治るから」 母の白い顔が微笑む。 「負けていられないもの」 ね、と京の手を取り、しっかりと握られる。 「でも……退院って」 そう聞いたのに。 「今夜、都も一緒にと思ったが、今……、話そうか」 近衛は、京を沙耶のベッドの端に座らせ、自分は傍にあったパイプ椅子へと腰を降ろした。京の手は沙耶に握られたままだ。 父親の口から、母親の詳しい病状や、これからのこと。そして再発の危険性。それぞれが、慎重に言葉を選んで語られてゆく。 「母さんの病気の第一人者と言われている医者が、今、……アメリカに居て、清田先生から、直接紹介してもらえる事になった」 その言葉の意味は、深く考えるまでも無い。 「私は、出来るだけのことをしたい。少しでも良い治療を受けさせようと思っている……。母さんも、治る可能性が増える事に期待しているし、今後、その方向で動こうと思う」 想像したとおりの言葉を告げられ、京はコクリと頷いた。 ――でも、でも……。そうしたら。 「こんな、私たちの都合で京たちを振り回すのは、……本当に申し訳ないと思っている」 父、近衛の言葉が図りかね、取り残されるような不安が胸を締め付ける。 またバラバラに暮らすのだろうか。また離れ離れになるのだろうか。また一人に……なるのだろうか。 「京も、一緒に行ってくれるか?」 「え……?」 驚いて母の顔を見ると、微笑んでくれた。父も頷いてくれる。 母親の優しい温もりと、父親の大きな手から伝わる安心感。 断る理由など、ある訳が無かった。 授業を終えた京は、帰り支度をしながら、姉の都と父との三人で話をした昨夜の事を思い出していた。 母親の退院は、もうすぐ可能だということ。ただそれは、完治としての退院ではなく、次の手術の為の準備期間であることは、忘れてはならいと念を押された。 これから数ヶ月を準備に費やし、冬になる前に渡米する。 現在大学院へ行っている姉は、休学して向こうの大学へと入りなおすつもりらしい。気になる研究があったので、渡りに船だったと喜んでいるのが流石だ。 当然、京も転校という事になる。この場合、書類が通れば、日本に戻る前の学歴のまま、ハイスクールへ編入という形が自然だった。父親だけは、完全にアメリカへ移る事が仕事上無理なので、必要に応じて行き来をする事になる。 ――またアメリカへ行くのか。 ぼんやりとその状況を想像して、ぽっかりと幼馴染のジェームスの顔が浮かんだ。 思わずフルフルと頭を振って、太陽の下で厭味なほど快活、且つ爽やかに微笑む彼のイメージを追い払う。 「どうした?」 はっとして振り向くと、見上げるほど背の高い友人が視野に入った。 「あ……」 「どうした?」 「……ううん」 突然、彼とも離れてしまうのだと気付く。 折角仲良くなれたのに。そう思わないわけではないが、不思議と寂しい感情が沸いて来なかった。勝也とは既に、時間や距離などがあまり関係ないくらい、身近なものになっているからかもしれない。 極端に急ぐ話題でもない。この話は今度、勝也が家に遊びに来た時にでも話せばいい。だから今はなんでもないと、そう答えた。 「ほんとに?」 疑うような顔で見つめられたが、少し微笑んで、大丈夫と頷いた。 「そうか」 「うん」 珍しく京が笑った事に安心したのか、勝也も精悍な顔を綻ばせる。 「……あ、そうそう。京ってピアノ弾けたよな?」 「?」 突然の話題にどう応えてよいか解らず、京は首を傾げた。 確かにそれなりに弾く事は出来る。勝也にも何度か戯れ程度に聴かせた事があるが、今されている質問の意味と、どう繋がるのかが解らない。 「生徒会と学祭実行委員会関係で、バンドする事になったんだよ」 「バ……、バンド?」 そう。と、勝也があまり乗り気ではないような風で、肩を竦める。 「ドラムとギター、ベースは居るんだけど、キーボードが見つからなくてさ」 「はぁ」 「京にやってほしいんだけど」 「は?」 もう一度言う? そう言われて、京は慌てて首をふった。 「バンド……って、キーボードなんて居なくてもいい様な……。それに、この学校だったら探せばそれなりに居そうだけど……?」 一応手伝える事があれば……とは考えていたが、あまり目立つような事はしたくないと、そう言う意味をこめて言ってみたが、勝也がそれを知らない訳がない。ましてや、京が嫌がることを、無理に押し付けることも無いだろう。という事は、なにか彼なりの理由があるのかもしれない。 「うん。だから京に声かけてみた」 「……俺、生徒会とか全然関係ないのに?」 当然の質問を返してみる。 「主催って事で、体裁が整えばいいんだよ。それに、メンバー的に訳アリばっか集めるから、あんまり無差別に声もかけられないし、基本的に上手い奴じゃないとダメ」 何気に気合を入れている所を見ると、勝也はこの「バンド」に対して、結構真剣に取り組んでいるらしい。最初乗り気に見えなかったのは別の意味があるのだろうか。 「ワケアリってなんだ……?」 「あー。まぁ見れば解るよ」 「……?」 「今度、メンバーに会わせるから、それで決めてもらってもいいし」 京の性格を知っている言葉に、思わず苦笑が漏れた。 ピアノは小学校に上がる前から習っていたが、自分では趣味の手慰み程度で、それほど上手とは思っていない。それでも良いのか? と聞くと、初見でそれなりに弾けるくせにと笑われた。 「やってくれる気になった?」 普段世話にばかりなっている勝也の、少しでも役に立てるなら。そう思って頷いた。 「ありがとう」 ぽんぽんといつものように頭を撫でられ、なんだかいつもより照れくさい。 「勝也のパートは?」 「…………あー」 「?」 珍しく歯切れの悪い勝也に、京は首を傾げた。 「ギーターと」 「と?」 「……………………ボーカル」 「うわ」 似合う、と京は笑った。その他のメンバーの名前を聞くと、京でも学内で名前を聞いた事があるような”有名人”ばかりで、勝也が不足パートを迂闊に誘えないと言った意味が解ったような気がした。 「おっと、時間ない。また詳しい話はあとでするよ。明日の放課後、空けといて。メンバーと顔合わせだから」 「うん」 「じゃな!」 ばたばたと、忙しそうに走り去ってゆく広い背中を見送りながら、京は改めて自分の身に起きた珍しい事態を、他人事のように受け止めていた。  祭りの準備へ向けて忙しく動き廻る勝也と、なかなかまとまった時間が取れない京は、個人的な話をする機会が持てないまま、時間だけが足早に過ぎていった。 京が加わる事になった「バンド」は、一年が勝也と京の二人。二年生が一人と、三年生が二人。どういった関係で集まったのか、はっきりした事は解らない。だが全員、京でも名前を聞いた事があるような、割と有名な人物である事は確かだ。 知らない人を避ける傾向にあり、更に他人の顔をおぼえるのが不得手な京だったが、いい感じに個性的な彼らは見た目どおり気さくで、ぎこちなくしか接する事の出来ない京に対しても、鷹揚に接してくれた。 何より、思ったよりも練習時間は少ない事にほっとした。その割りに元々上手いメンバーが集まっているのか、端で聴いていても危なげはなく、それなりにまとまりがあるのが面白い。 ドラム、ベース、キーボード、そしてツインギターの五人構成。ギターの一人が勝也で、ボーカルを兼ねている。 どうやら彼らの会話を聞いていると、無理矢理勝也に押し付けたという感じだった。 「どうして?」 そう聞くと、勝也が肩を竦める。 「さぁ、一番年下だから……かな」 窓際でギターのチューニングをしていた、三年の一人がクスクスと笑いだす。 「……?」 「お祭りだからなー。舞台に上がっている間は、色々安全なんだよ」 「??」 「解んない?」 本当に解らなかったので、素直に「うん」と頷く。 「いい意味でも悪い意味でも、ここに居るやつらは目立つんだよね。本人の意思関係なく」 「嵯峨チャンなんて、もうモテモテで……」 「やめろよ……」 本気で嫌がっている風の三年生の一人が、頭を抱えるように項垂れる。 どうやら彼は、本命の彼女が居るにも拘らず、他校生の少女たちから熱烈なアピールを浴びせかけられている存在らしい。 「隠れていると、余計エスカレートするからなぁ……」 「完全に隠れられるわけじゃないしね」 「”鬼ごっこ”状態とか最悪」 あぁ……と、昨年のことを思い出したらしい上級生が顔を曇らせる。彼は去年、言葉では言えない様な目に遭ったようだ。 「そう。だから、参加することが公表できて、且つ適当に”顔見せ”が解ってる状態じゃなくちゃダメなんだよ」 そのための舞台なのかと驚く。 「なんか……すごい」 唖然としたように京が目を見張ると、他のメンバーたちがクスクスと笑う。 何が可笑しいのかと勝也を見ると、「本人自覚ないし」と笑われる。 「京も安全だよ。後夜祭まで大義名分付きで控え室確保したから。そこ、お祭り開催中は関係者以外立ち入り禁止」 「あ……」 解った? と悪戯っぽく微笑まれる。 「普段はなんとかなるけど、祭りの最中はね。……特に後夜祭は、結構皆箍外れてヤバイって聞いたし」 あの更衣室での出来事のような事が起きないように。仮に何かが起きても、安全に逃げこめる場所を作ってくれたのだと解った。 「もう解ったと思うけど、ここのメンバーも、理由はそれぞれ違うけど、煩わしいのから逃げたい奴ばっか」 「そうでもなきゃ、目立つ役どころを俺に押し付けたりしないで、他のとこみたいに全員ボーカルやりたがるって」 もう二組いるバンドたちの事を指して勝也が笑うと、他のメンバーも同じように笑った。 「学園祭って……そんなに危ない……の?」 その手の祭りは経験がない。人が沢山来るという話は聞いていた。だが、身の危険まで想定するなど、考えても居なかった。 大丈夫。と大きな手に頭を撫でられる。 「脅してごめん。なんというか、そうだなー……大体は、普段は入って来れない女の子たちが、キャーキャー騒ぐ程度だよ」 耳に馴染まない黄色い声を思い出し、京は微かに身震いする。 「でもさ、……安全に越した事はないし、もし俺の見てないところで何かあったら、本気で嫌だから」 「……ごめん」 役に立つつもりで居て、結局はお荷物だった事に気付かされる。 「あ、もしかして、また迷惑かけたとか思ってる?」 図星を指されて、京は困ったように下を向いた。 「それは違う、信じてよ。キーボードが見つからなかったのも本当だし、京をこのバンドに入れたかったのも、メンバー全員の希望だからさ」 「……?」 訝しげに勝也を見ると、ニヤリと笑われる。 「京を連れて来れるかもって言った時の、先輩たちの喜んだ顔。そりゃもー傑作だったぜ?」 「……??」 「勝也、よくやった!! って思わず褒めちゃったよ」 褒めるなんて意地でもしたくなかったのになーと、メンバー唯一の二年生が悔しそうな顔をする。 「そうそう」 「な? 京が入ってくれて、みんな大喜び」 喜ぶ理由が解らず、京は困ったまま首を傾げた。 |
|
|
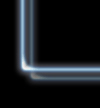 |
|
 |