 |
 |
|
 Peaceful Days -7 Peaceful Days -7
担任から教えられた京の家の住所は、勝也の自宅からそれほど遠くない場所にあった。あまり足を運ばない地区ではあったが、近所なので大体の見当は付く。  とりあえず、と京は勝也を自分の部屋へと案内した。途中、小さい頃から家のことや母の手伝いをしてくれている雪塚が、タイミングよくお茶とお菓子を持たせてくれたので、そのまま二階へと上がった。 「はいこれ。宿題は特にないけど、通達は早目に目を通しておいて」 勝也からプリントを受け取る。 「ありがとう、わざわざごめん」 「いや、様子気になってたし……。思ったより元気そうでよかった」 「……ん」 更衣室では、みっともない所を見せてしまったので、気遣いでも元気そうと言われて、少し安心した。 「なんか凄い部屋だな」 広過ぎるほど広い部屋を見回し、勝也がポソリと言う。京は恥ずかしくて、思わず俯いてしまった。 「どうした?」 「あ、いや……なんか、ちょっと」 絵に描いた道楽息子みたいだから、と京は自分の状態を受け入れていないような、ほんの少し困った顔をした。 帰国にあわせて、京のためにと両親が用意してくれた部屋は、驚くほど立派なものだった。最新型のオーディオに、液晶テレビ。学習机とはとても呼べない、一生物のデスク。天井まで届く、壁面いっぱいの可動式の本棚。一人で寝るには大き過ぎるのではないだろうかと、疑問を感じてしまうようなサイズのベッド。主はどこのエグゼクティブだと聞きたくなるような、高価な家具で全てが調えられているのだ。 しかもこの家自体、アメリカに行く前に住んでいた場所ではなかった。新しい土地に建てられたこの家は、日本でありながら、神経質なほど防犯設備が整っている。それだけあの頃の状況が酷かったという事になるのだろうが、解っていても、その設備に面食らう。 しかしこれも全て、両親が京の為を思い用意してくれたことなので、多少やりすぎだよと思わないではないが、当然感謝もしていた。 「まぁ、……そんな事も無いんじゃない?」 そうかなぁと、京が眉を顰める。 「だって居心地いいじゃん、この部屋」 その言葉には、お世辞でも嘘も感じられなかった。 大きな窓と部屋の広さ、天井の高さと家具の配置バランス。全てが絶妙で、本当に気持ちが良い。 良いところばかりで、どこもおかしい物は無いが、ひとつだけ、どうしても面白いと思ってしまう場所があった。大きなベッドである。この大きなベッドに、小柄な京が眠っているのかと思うと、勝也は笑いが込み上げてきて、堪えるのに苦労した。きっと隅っこのほうで、仔猫のようにちんまり丸まって寝ているに違いない。かなりの確立で当たっているだろう想像を止められず、笑わないように我慢している勝也だったが、それに気が付かず、神妙な顔は気を使ってくれているのだと、勝手に申し訳ないと想像した京は、「何もかも大きくて」と曖昧で微妙に噛みあわない返事を返すという、穏やかで不思議な時間が流れた。 しばらく、所在なげに本棚に並ぶ様々な本の背表紙を眺めていた勝也が、「あぁそうか」と、なにかを思い出したように言った。 「……?」 「英語の本が多いと思ったら、そういや、アメリカに居たんだよな」 「あ、う……ん。何年か」 「そうか。長期間行けるっていいよな」 「……ん」 これ以上深く説明を求められたらどうしようと、つい身構えてしまう。今のことなら少しは話せるかもしれないが、それでもやはり躊躇いがある。 「あっちの部屋は何?」 ドアのない壁の向こうにある部屋を指差された。 「え?」 突然違う話題を振られ、少し驚いた。同時に、ほっとしてしまう自分があからさまに思えて、京はなんだか申し訳ない気持ちになる。 「マシンが……置いてある」 「あ、学校で聞いたアレか!」 嬉しく弾む声に驚き、京は小さく目を見開いた。 勝也と学校で話す内容のほとんどは、コンピューターに関するものばかりだった。同じ年で、プログラム言語まで話が通じる相手は、勝也が初めてだったので、良い意味で意外だった。勝也も同じように思ってくれていたら良いなと、京は心の隅で思っていたが、まだそこまで聞ける気安さはない。 「見る……?」 「いいのか?」 「うん」 触れられて嫌なものは無いし、見られて困るようなものには、何重にもパス設定してある。 「うお。何台あるんだ……。あ、この辺のって自作? CPUはなに? ハードとメモリは幾つ積んでるんだ?」 「……勝也」 さっきとは別の意味で、京は驚いていた。 なんだか、可笑しい。こんな楽しげな勝也を見るのは初めてだった。いつもは驚くほど落ち着いて大人っぽい彼が、こんな風になるなんて信じられない。こんな姿を、一体どれだけの人が見た事があるだろうか。京は少し得をしたような気分になり、ふふ……と笑った。すると振り向いた勝也が、何故か不思議な顔をして、その後ニッコリと笑った。 「へぇ」 「……?」 「いや、良いなと思って」 意味はよく解らなかったが、勝也がとても楽しげなので、京も嬉しくなり、これはきっと悪い事ではないのだろうと、そう思う事にした。 その日を境に、勝也はよく京の家へ遊びに来るようになった。 母親の事が気がかりで、あまり家の外に出たがらない京に、勝也があわせてくれているのだろうが、時間もまちまちで気ままなのが気楽だった。 すぐに夏休みに入った事もあり、ふらりとやってきた勝也と二人、学校から与えられた膨大な課題を、数日で一気に仕上げてしまった事が、更に互いの距離を縮めたようにも思う。 持て余す休みを使い、話が合うまま何日もかけてコンピューターの最新事情を調べ、複雑でマニアックなソフトを延々と設計し、逆に反動のように、ふざけたゲームを作って遊んだりもした。あの空き地に居る時と同じように、特に何もしないで、ただのんびりと過ごす時もある。 京が海に潜るのが好きだと知ると、勝也はそれにも興味を示してくれた。 今までに潜った事のある海の写真を、興味深げに眺める勝也の隣に座りながら、京は今まで感じたことの無い、穏やかな時間の流れを感じていた。 「色々な所に行ってるんだなー」 「うん」 「結構、イルかとかクジラとか写ってるけど、そういう所狙って行くわけ?」 「ううん……でも……なんか来る」 「来るって?」 「船で沖に出たり、潜ってると来る」 「へえ。ポイントに行っても、簡単に会えるもんじゃないって聞いてたけど、意外とそうでもないのかな」 「どうだろう?」 解らない。と首を傾げると、ぽんぽんと頭を撫でられる。 「京に会いに来るのかもよ?」 「まさか」 「いや、この間テレビで”クジラに会いにいく”とかドキュメントやってたんだけど、タレントの誰だっけかな? 一週間もクルーザーに乗って頑張ってたのに、全然会えなくてさ。時間の穴埋めに出てくるのは、水族館の人懐っこいイルカとか熱帯魚ばっかり。ラストでようやく、遠ーーーくに尾びれが見えたのと、ぶしっと何度か潮吹きがだけだったぜ?」 「それは……運が無いね」 気の毒にと京は肩を竦めた。 「ほらこれなんて、マンタと一緒に泳いでるじゃん。綺麗に撮れてるなぁ……」 あぁ、と頷く。ゆったりと羽ばたくように泳ぐ、巨大なマンタの群れの中に、フィンをつけた京の小さな姿が見える。 「そういう写真が撮りたかったんだって」 アメリカで知り合ったダイビング仲間の一人が、プロの水中カメラマンだった。 「プロの人の写真か。道理で綺麗だと思った」 「青の色がすごい」 「そうだな」 そのカメラマンとは、京と一緒に潜ると良い写真が撮れると、やたらと気に入られてしまい、一緒に海へと潜る事が多かった。 京にしてみれば、自分が写真に写る事自体が嫌だったので、何度も断ったのだが、どうしてもと、しつこく毎日毎日口説かれ、根負けした。絶対に顔を写さず、自分と解らない状態であれば、撮ってもいいという条件だったが、大の大人に、泣き落としされたというのが本当の所だ。 勝也が眺めるアルバムのページには、絶妙のバランスを描く、真っ青な空と海の境界線で、ウェットスーツを着た後姿の京が、イルカの背びれに手をかけた状態で写っている。次のページを捲ると、蒼い海の中、逆光に浮かび上がる大きなクジラと京のものらしい小さな身体があった。 「京だって解るけど、顔写って無いのばっかりだな」 「……写真嫌い」 ポソっと正直に告げた言葉に、勝也は微笑みながら「そうか」とだけ答えた。 京にとって、勝也という人物は今まで会った事の無い、不思議な相手だった。 約束の無い自由な時間の共有。負担にならない適度な距離。生まれて初めて知る感覚だったが、それがとても心地よかった。 意識せずに「親しい友人」という形が、自然と出来上がってゆく。多分、お互いが居心地の良い相手である事を、無意識に感じていたのかもしれない。 以前、勝也から感じていた「気をつけている」という視線も、今はもうなかった。プライベートで、一緒に居る時間が増えたからなのだろう。 さりげなく京をフォローしてくれる勝也は、全身全霊、頑迷なまでの使命感で”守る事”をアピールするジェームスとは、まったく違っていた。常に自然で安定した距離を保ち、京が自分で何か行動する意味を考えて、必要な時にだけ力を貸してくれる。 こんな人は初めてだった。一緒に居ると楽しいと思う。今まで誰と居ても、そんな気持ちを感じた事がなかったのに。 何故だろうと、京は我が事ながら首を傾げてしまうが、理由はわからなかった。けれど、これはこれで、はっきりしなくても良いような気がする。 こうして勝也と一緒に過ごす事により、自分は変われるのかもしれない。越えられない壁の向こうを、見る事が出来るのかもしれない。 何かが変わる予感。それを期待しまうほど、京の中で勝也という友人の存在は大きくなっていった。 夏休みという纏まった期間、落ち着いて穏やかな勝也の気質に触れていたせいか、京は今までに無いほど、精神の安定した日々を送れるようになっていた。 当然、父、近衛も勝也の事が気に入り、遊びに来ていると解ると、やたら機嫌が良い。口には出さないが、もしかしたら勝手に息子が増えたような、そんな気になっているのかもしれない。 雪塚も、京があまり大きく体調を崩さ無くなった事を、本当に喜んでいて、勝也のお陰だと、何かとサービスが良かった。いつの間にか家の中に、勝也用の食器やスリッパが揃っていたのには驚いたが、当の本人は喜んでくれたし、京にしてみれば、家族の心遣いが嬉しいだけだ。 さりげない喜びがある、穏やかな日々。 ”笑う”という事がどういうことだったか、少ずつ取り戻せてきた感触。一歩一歩、おぼつかない足取りだが、ゆっくりと感情の起伏が蘇えってくる。 だから。 少し油断していたのだ。 いつまでも過去に捕らわれていたくない。 もう大丈夫だと、……そう信じたかったのかもしれない。 それは、夏も終わりに近づいた、ある日に起こった。 |
|
|
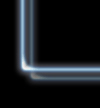 |
|
 |