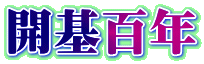

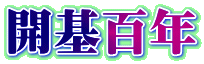

治安と法務 交通安全 消 防 災害と防災 住民活動 集落の歴史と自治活動
| 第9編 | 公安と防災 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 |
治安と法務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 警 察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犯罪の発生状況 遠軽警察署管内(7町村)における平成8年(1996)の刑法犯発生は331件で同元年(1989)以降減少傾向にあったが、同7年(1995)から増加に転じている。 同8年は窃盗が圧倒的に多く314件で全体の95%を占め、次いで粗暴犯が8件、知能犯が5件、その他4件となっている。 この増加は、窃盗が前年より一挙に同7年に84件、同8年に44件も増えたことによる。 管内地域別犯罪の発生状況では、人口が最も多い遠軽町に集中している。 昭和60年(1985)から平成8年までの12年間は管内の55.9~73.6%を占め、同8年は55.9%であった。 上湧別町は、昭和61年(1986)を除いて、常に管内2番目と多く、5.5~19.7%という発生割合を記録している。 発生件数は、同59年(1984)の109件を境に減少傾向にあり、年によって増減はあるもののほぼ20~70件台にとどまっている。 上湧別著王ないの平成8年の犯罪発生状況は、40件で前年より13件増加している。 このうち乗物盗11件、自販機荒らし8件、かっぱらい4件、次いで事務所荒らし2件などが報告されている。 少年非行の補導状況は、昭和57年(1982)以降、全体として減少傾向にある。 平成8年の上湧別町内での少年非行の補導は、深夜徘徊の6件のみであった。 このほか、遠軽警察署が平成8年に検挙した特別法犯は14件あった。「水産資源保護法」違反5件、「覚醒剤取締法」違反4件、「漁業法」違反3件、「銃刀法」違反1件などである。 検挙件数としては昭和50年代(1975~)に比べ、大幅に減っているが、平成に入ってからは若干増える傾向にある。 警察官駐在所 上湧別町内には、北海道警察北見方面本部遠軽署の出先機関として、中湧別駐在所と上湧別駐在所が配置されている。 中湧別は2人、上湧別は1人の常駐の3人体制で、両所にパトロールカー1台、無線機1台、受令機1台が配備されている。 平成7年(1995)から役場所在地にある上湧別駐在所には警部補が配置され、所長として警察業務を統括している。 犯罪捜査や犯罪・事故の取締り、防犯や事故防止の指導などに当たるほか、住民の相談窓口としても地域に密着した活動を行い、住民に親しまれる交番を目指している。 中湧別駐在所が昭和57年(1982)に改築されたのに次いで、同63年(1988)には上湧別駐在所が新築されている。 特に上湧別駐在所の建物は、ドーム型の玄関フードをつけたユニークなデザインが注目され、当時”おしゃれ交番第1号”といわれた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 防犯活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防犯協会 遠軽地区防犯協会上湧別町支部は、昭和28年(1953)に結成されている。 犯罪のない明るく住み良い町づくりを目指して、各関係機関、団体の協力を得ながら防犯思想の普及、犯罪の防止活動に自主防犯の立場から取り組んでいる。 毎年4月ごろ支部総会を開き、前年度の事業・決算報告、当該年度の事業計画・予算を審議して決定するほか、情報交換などを行っている。 支部長は上湧別町長が務め、副支部長は助役と上湧別、中湧別の両分会長の3人が選任されている。 理事、監事を含めた役員については任期2年となっている。 規約上、代議員の任期と定数はなく、支部長が委嘱している。 平成9年(1997)4月1日現在では支部長、副支部長のほか、理事14人、監事2人、代議員46人の構成である。 毎年実施している事業は、防犯チラシ、町広報、看板、防犯旗、広報車などによる啓蒙宣伝活動をはじめ、防犯パトロールの実施、青少年健全育成と非行防止活動の推進、悪徳商法からの高齢者被害防止活動の推進などである。 これらの活動は、春、夏、全国、歳末の各防犯運動に併せて行うほか、お盆、秋祭りなどの諸行事においても防犯パトロールを中心に実施している。 主な防犯活動 毎年6月下旬に展開される防犯運動・自転車総合対策強調旬間では、自転車防犯診断、防犯標語書道展、防犯パレード、街頭啓発、自転車防犯点検などを行っている。 7月に1ヶ月間実施される青少年の非行防止道民総ぐるみ運動では、特別補導、キャンプ場などの巡回指導、街頭啓発、自転車防犯診断のほか、社会を明るくする運動パレード、青少年非行防止吹奏楽演奏会などで趣旨の徹底を図っている。 10月11日から20日までの全国地域安全運動では、老人クラブ会長とも地域安全意見交換会、全国防犯功労者表彰伝達、乗物盗防止事業所訪問、住宅防犯診断、防犯パトロール、自転車の防犯診断と防犯登録促進、小中学生の防犯標語作成など多彩な行事を繰り広げている。 恒例の歳末防犯運動は、毎年12月1日から31日の大晦日までである。 年の瀬の犯罪を防ぐため、金融機関強盗模擬訓練、盗難等防止家庭訪問、防犯診断、少年補導、防犯パレード、防犯パトロール、車両防犯診断などを実施している。 防犯の町宣言 町民の防犯意識を高め、犯罪をなくして明るい町を実現しようと、昭和63年(1988)3月16日、上湧別町議会は「防犯の町」を決議した。 遠軽警察署管内の7町村が一斉に議会で取り上げ、乗物盗、車上ねらい、空き巣などが各町村で多発していることから、遠軽警察署と遠軽地区防犯協会が呼びかけて実現したものである。 「防犯の町」宣言文は、次のとおりである。 私たちの日常生活が平穏かつ安全であることは、町民共通の願いである。 しかしながら、社会情勢の目まぐるしい変化に伴い、犯罪は一向に減少する傾向がみられない。 上湧別町は、町民の平穏で安全な日常を確保するため、町民一致の協力で、青少年の非行防止、長寿社会に対応した高齢者の犯罪被害防止などに努めるとともに、防犯思想の普及高揚を図り、犯罪のない明るく住みよいまつづくりを決意し、ここに防犯の町を宣言する。 以上決議する。 昭和63年3月16日 北海道紋別郡上湧別町議会 暴力追放推進協議会 上湧別町内では、昭和56年(1981)ごろから暴力事件が多発し、同58年(1983)1月には暴力団構成員らが逮捕されるという事件が起こった。 これは、北海道で以前から勢力を伸ばしていた暴力団に対し、関西系の暴力団が新たに北海道に進出し、上湧別町にも入り込んで抗争事件を引き起こしたものである。 不安を募らせた町民は、「暴力をこのまま放置すれば、暴力の絶えない町になってしまう」と立ち上がり、上湧別町暴力追放推進協議会を結成することになった。」同協議会は昭和58年5月、田中重一(防犯協会中湧別分会長)を会長として発足した。 自治会、婦人会、教育委員会、学校、消防団、商工会、農協など町内の各団体の代表者がメンバーとなった。 事業としては、①暴力団には一切金を出さない、②暴力団を利用しない、③暴力団に施設を利用させない、④暴力団には泣き寝入りしない、を重点目標に、約30店ある飲食店組合加盟店入り口に「暴力追放の店」の看板を出したほか、立て看板、チラシなどを実施している。 暴力犯罪の防止に結束した町民の意識高揚を背景に、上湧別町議会は平成5年(1993)4月に、次の「暴力追放に関する決議」を可決した。 私たちの日常生活が平穏で、かつ安全であることは町民共通の願いであります。 しかしながら、最近の社会情勢において犯罪・暴力は一向に減少する傾向がみられず、中でも暴力団は、ますます資金源犯罪の悪質化、巧妙化、潜在化傾向を強め、町民に多大の不安を与えております。 暴力行為のない住みよい郷土を築くことは、全町民の願いであり、住民生活を脅かす暴力行為は、町民の切なる願いである安全で明るく住みよい町づくりの実現のためにも、断じて許すことはできません。 よって、我々は、町民が安心して暮らせる「暴力のない安全で平穏な地域社会」の実現のため、町民及び関係機関と一体となって、広範な運動を推進し、暴力団の根絶に向け、全力を尽くすことをここに決意するものであります。 以上、決議する。 平成5年4月26日 北海道紋別郡上湧別町議会 こうして暴力団の追放運動は、さsらに強化された。 平成6年(1994)から上湧別町暴力追放推進協議会と上湧別、中湧別両祭典委員会が遠軽警察署の協力のもと、秋祭りの露店から暴力団関係者の出店を完全に排除することを決めた。 この方針に基づき、出店を希望する露店商からあらかじめ出店申請書の提出を義務づけて厳しい審査を行い、出店場所の区割りや電気設備などについても、両祭典委員会が事前に指定し準備するなど、従来の露店商主導型から地元祭典委員会主導型へと変わった。 これにより、同年以降、上湧別町の秋祭りから暴力団関係者の露店はすっかり締め出された。 防犯推進委員 防犯協会の組織の一つとして、昭和40年(1965)から防犯連絡所が設けられていた。 町民総ぐるみできめ細かな防犯活動を推進するため、各地域の責任者宅に防犯連絡所を配置(昭和51年度は71ヶ所)、犯人、挙動不審者、押し売り、酔っ払い、家出人、迷子、負傷者、病人、非行少年や不審車両などをみかけたときに連絡してもらうというシステムであった。 この制度は、平成元年(1989)3月1日から防犯推進委員制度に改められた。 それまでは防犯連絡所という場所に重点がおかれていたが、これを防犯推進委員という人に視点を置き換え、さらに委嘱の主体を遠軽地区防犯協会長から遠軽警察署長と遠軽地区防犯協会長の連名によるものに変え、権威を持たせるようにした。 防犯推進委員は、おおむね60世帯の居住区ごとに1人の割合とし、40人程度に委嘱しているが、それぞれの住宅などに防犯連絡所の標識を掲示、事件や事故の発生や不審な事物などの通報、住民からの要望や相談に応ずるなどの活動を行っている。 この防犯推進委員は、さらに平成8年(1996)4月1日から地域安全活動推進委員と名称を改め、より幅広い活動を目指している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | その他の司法機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人権擁護委員 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視し、万一侵犯された場合は、そおの救済のため必要な措置を講じ、また、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としている。 任期は3年で、活動は秘密を守り、厳正公平であることがもとめられている。 人権擁護委員は、市町村長が議会の同意を得て推薦した者を法務大臣が委嘱する。 上湧別町は、昭和48年(1973)に法務省から人権モデル地区に指定され、5年間にわたり自由人権思想の普及に努め、その徹底を図った。 北見人権擁護委員協議会と釧路地方法務局北見支局は、毎年網走支庁管内各市町村でで特設人権相談所を開設している。 上湧別町でも毎年1回開かれており、町内から選任されている人権擁護委員と法務局職員が、相談に応じている。 北見人権擁護委員協議会は毎年、特設人権相談所の開設のほか、ポスターやリーフレットの作成配布、作文(中学生)、書道(小学生)の募集、講演会・座談会の開催、委員研修会の開催などの事業を行っている。 調停委員 社会が複雑になり、価値観が多様化するにつれ、人間関係をhじめらゆる生活の分野でトラブルが急増してきた。 しかし、裁判に持ち込めず問題解決の糸口さえ見いだせない人たちも多い。 こうしたもめごとの当事者が、調停委員会の斡旋のもとに話し合い、お互いに譲り合って妥当な解決を図る制度が調停である。 調停委員は、地方裁判所または家庭裁判所が選任している。 遠軽地区では、調停委員による協議会が結成されていて、担当地区を決めて調停に当たっている。 保護司 昭和25年(1950)に公布された「保護司法」に基づき、法務大臣から委嘱されるのが保護司である。 過って罪を犯した人たちを、奉仕の温かい心で励まし、再び犯罪を起こさせないよう相談相手になるのが仕事で、任期は2年である。 上湧別町は、釧路保護観察所遠軽保護区に管轄下にあり、保護司は現在5人に委嘱されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 topへ |
交通安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 交通事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発生状況 交通事故は以前として増える傾向にある。 様々な交通安全運動が展開され、交通安全設備の施設が進み、交通指導や交通取締りが強化されているにもかかわらず、事故防止の願いは思うように達成されていない。 平成8年(1996)は、北海道内、網走支庁管内、上湧別著王ないとも発生件数、死者数、傷者数のすべてが同7年(1995)に比べて減少している。 町内の事故 平成8年(1996)の1年間における上湧別町内の事故は、発生件数23件で前年より5件減少した。 傷者32人は、前年より8件の減少であった。 事故の原因をみると、前方不注意、ブレーキ操作の誤りなど安全運転義務違反が17件で最も多く、次いで交差点徐行違反、最高速度違反、交差点安全通行違反、歩行車保護違反、追い越し違反、その他の違反が各1件となっている。 事故の類型別では車どうしの事故が14件でトップ、車と自転車の衝突が5件、横断中、車両単独各2件となっている。 また、第1当事者のうち50歳代が8人、16歳から24歳が4人、25歳から29歳、60歳から64歳各3人、30歳代、65歳から69歳各2人、70歳代1人となっている。 この結果、50歳代以上のドライバーが14人で半数以上になっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 交通安全協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通安全協会 北海道交通安全協会遠軽地区支部が設立されたのは、昭和23年(1948)である。 当時は遠軽警察署長が支部長を兼務、会員は自動車の所有者、運転免許の所有者で構成されていた。 車両台数もドライバーもまだ少なく、活動は交通法規の周知や交通道徳の高揚などが主となっていた。 同27年(1952)7月、同支部は遠軽地区交通安全協会と改められた。 車両の増加が目立ち、交通事故が次第に増えてきたのは昭和30年(1955)以降であった。 遠軽地方でも交通事故が徐々に社会問題化したのは同30年代の後半に入ってからで、同38年(1963)に発足した上湧別町交通安全推進委員会とともに、地域の交通安全対策を担う役割が大きくなった。 交通安全協会は、交通安全の確保と交通秩序の維持を通じて地域交通文化の発展を目指すことを目的としている。 具体的には交通安全指導車を走らせて街頭啓発活動を行ったり、関係諸法規の周知徹底、交通道徳・順法精神の高揚、優良運輸関係従事者・交通功労者の表彰などに取り組んでいる。 会員は通常会員、協会の趣旨に賛同する者、自動車運転者団体による賛助会員で構成されている。 各町村にはその地域に応じて支部が置かれている。 上湧別町には上湧別、中湧別の両支部が設置されていたが、交通事故が多発し、事故系地が複雑化する中で、効率的にそれらに対応するため、また1町村1支部が主流になってきた。 そこで、上湧別支部一本化の方向が検討されることとなった。 平成6年(1994)12月13日、上湧別、中湧別両支部合併についての打ち合わせ会議が始まり、「両支部合併問題専門委員会」、「両支部合併問題常任委員会」が設置された。 翌7年(1995)3月から、数回にわたり両委員会において、会則素案・構成などが協議され、同年11月29日に最終的な原案が整い、同8年(1996)4月12日から一本化が図られて全町民加入による遠軽地区交通安全協会上湧別支部となった。 上湧別支部は平成8年3月14日、中湧別支部は同年3月15日に解散した。 交通安全推進委員会 高度経済成長の波に乗って乗用車を中心とした車両の国内生産が急増、家計にゆとりが出てきた国民の間でも自家用車が増え、これに伴い交通事故の発生が深刻な社会問題になった。 国は昭和38年(1963)6月、「地方自治法」の一部を改正して、地方公共団体に交通安全保持のため適切な施策を講じることを義務づけた。 この方針に基づいて同年10月6日、関係機関、各種団体、各企業などが結集して上湧別町交通安全推進委員会を設立した。 遠軽地区交通安全協会中湧別、上湧別両支部と協力し合い、街頭指導や広報・啓発活動、交通安全教育、安全施設の整備など幅広い事業に取り組んでいる。 具体的な取り組みとしては、①交通安全家庭新聞を町内全家庭配布、②保育園児対象に腹話術などによる楽しい交通安全教室の実施、③新入生児童に蛍光ランドセルカバー・交通安全教育教材の配布、④町内各老人クラブに夜光反射材・交通安全リーフレットを配布して警察官との懇談会実施、⑤小・中学校児童生徒によるオホーツクセーフティーロード作戦で、通過車両などに対し交通安全を呼びかけ、児童生徒の交通安全意識の醸成と定着を図る体験学習実施などがある。 同委員会のメンバーは、会長を務める町長のほか副会長(1人)、理事(若干名)、監事(2人)、委員(若干名)となっている。 活動費には町費補助と寄付などが充てられている。 交通安全指導員 車両台数の増加に伴い交通事故の発生も多くなり、深刻な社会問題となってきた。 遠軽警察署は、これらの監視と指導のため、昭和31年(1956)、各町村の有志に委嘱し、交通安全指導員を配置した。 交通安全指導員は、朝夕、街頭に出て交通安全の確保に努めたが、交通整理誘導のほか各種行事への参加協力など活動量が増加する一方で、身分保障もなく無報酬であったため、待遇の改善が求められるようになった。 上湧別町は、昭和44年(1969)7月1日から「上湧別町交通安全指導員設置条例」と「上湧別町交通安全指導員規則」を施行し、待遇の改善と身分保証を定めた。 それによると、身分は非常勤特別職とされ、報酬や出張などに伴う費用が支給されることになった。 平成9年(1997)4月1日現在の年額報酬は、指導部長10万7800円、副指導部長10万1400円、指導員9万6000円である。 定員は22人、任期は2年となっている。 指導員には制服が貸与され、交通安全思想の普及と街頭指導を主な職務としてる。 毎月の定例街頭指導をはじめ安全運動期間に歩行車と自転車など軽車両の交通指導、登下校時の児童生徒の誘導、非常災害時の街頭指導など重要な役割を果たしている。 その出動回数は毎年約90回に及んでいる。 交通事故死ゼロ運動 交通災害の中でも、最も悲惨な結果を招く死亡事故を、何とかゼロに抑えようという交通事故ゼロのキャンペーンが、大々的に取り上げられるようになったのは昭和50年(1975)ごろからである。 網走支庁管内は数多くの観光地、行楽地を抱えているため、6月から10月にかけての期間(年によって異なる)に事故死ゼロ100日を設定し、住民参加の交通安全運動を展開した。 この期間中、事故死ゼロを達成した市町村には、網走支庁地区交通安全推進協議会から感謝状、記念品が贈られた。 当時、上湧別著王における事故死ゼロの記録は406日(昭和47年4月18日~同48年5月28日)であったが、昭和50年4月9日から始まった同運動では、この100日運動と併せてゼロ目標を1000日に設定し、家庭、職場、地域が一体となって町ぐるみで取り組んだ。 新記録達成を目前にした翌51年(1976)4月4日には、上湧別町、上湧別町交通安全推進委員会、遠軽地区交通安全協会上湧別・中湧別両支部が共催して交通安全町民大会を上湧別町社会福祉会館で開き、参加した町民代表約320人が事故死ゼロへの決意を誓い合った。 こうした町民の熱意が実り、昭和50年4月9日から続いていたゼロ記録は、同53年(1978)1月2日に見事、目標の1000日を達成した。 これを記念した交通安全町民大会は6日後の1月8日、上湧別町社会福祉会館で開かれ、新たに目標を1200日と定めたが、同53年4月2日に5の3の国道で湧別町在住の2人が死亡するという事故が発生、記録は1089日でストップした。 この記録は、平成に入ってからの1177日に次ぐ上湧別町における2位に当たる。 その後も毎年知恵を絞った運動を繰り返し、警察と連携して指導や取り締まりを強化した。 また、重大事故が発生すると非常事態を宣言したり、町民決起大会を招集し、気持ちを引き締めた。 非常事態宣言は、お年寄りを含む町民4人が輪禍の犠牲になった昭和63年(1988)と2日間連続して死者を出した平成元年(1989)に町長が出している。 上湧別町交通事故非常事態宣言 交通事故のない快適な地域づくりは、住民すべての願いです。 しかし、北海道の交通事故による死者は、すでに500人を超える尊い人命が失われています。 また、本町においても12月4日町内で死亡事故が発生し、今年、4名の町民が交通事故により尊い人命を失っており、本町にとっては、昭和46年以来の極めて憂慮すべき事態であります。 これから季節的にも一段と事故の発生が懸念されるところから「上湧別町交通事故非常事態」を宣言するとともに、悲惨な交通事故の防止に総力を挙げて取り組んで参る決意であります。」」町民のみなさんもこの非常な事態を重視して、一人ひとりが、人の命の尊さに思いを新たにし、運転者も歩行車も交通ルールを厳守し、交通事故に「あわない」「起こさない」運動を家庭、地域、職場、団体等で展開し、町民一人ひとりが交通安全意識を高め、自らの事故防止に努力されることを切望します。 右宣言する。 昭和63年12月8日 上湧別町長 佐々木 義照 こうした町民の決意にもかかわらず、翌平成元年5月11日と12日に連続して死亡事故が発生したために、同月13日に急遽交通事故死非常事態町民決起大会を開催すると同時に、交通安全町民署名運動に立ち上がった。 その結果、7115人の町民のうち82.3%に当たる5859人の署名を集め、遠軽警察署へ届け、町民の決意を改めて伝えた。 平成8年(1996)4月1日現在の上湧別町における交通事故死ゼロ最長記録は、同年5月13日から同4年(1992)8月1日までの1177日間である。 これは、記録がスタートした前々日と前日に連続して起きた死亡事故を教訓として、町民が必至に一丸となって努力した成果であった。 1200日の大記録まであと23日という同4年8月2日午前10時20分ごろ、札富美会館前の町道で、おがくずを積んだ普通トラックが路外に逸脱横転して町外の運転者が死亡した事故で、この大記録はストップした。 平成4年以降は交通事故の発生が続き、毎年の交通事故死ゼロ運動を500日と設定して、まずその目標突破に取り組んでいる。 同8年5月20日、目標500日を達成、次の目標を1000日と設定してゼロ運動を展開している。 同9年(1997)7月1日で907日である。 町ぐるみの運動 全道的に交通事故防止運動が展開されるようになったのは、昭和37年(1962)に交通安全道民運動推進委員会が結成されてからである。 上湧別町でも同年から広報「かみゆうべつ」などを活用して、交通安全キャンペーンを展開、翌38年(1963)に上湧別町交通安全推進委員会が発足すると、遠軽地区交通安全協会上湧別・中湧別両支部、交通安全指導員が一体となって本格的な運動を推進した。 これに呼応して昭和42年(1967)から子ども会交通安全駅伝競走大会が毎年開催されるようになったのをはじめ、同51年(1976)、建設業の経営者と従業員で組織している建設友の会が、マイカーによる事故防止のため「私用車両運転管理部会」を設立、同53年(1976)、みのり幼稚園では町内初の幼児交通安全グループの「こぐまくらぶ」を結成して、独自の活動を始めた。 地域住民の間でも交通事故防止の意識が高まり、昭和51年ごろまでに上湧別(現、屯市)、池内、南町、中町、北町、中鉄、東町の7自治会に交通安全部会が設置され、交通安全座談会や事故防止研究会などの開催、安全声かけ運動の展開などに取り組んだ。 このうち上湧別自治会は、同53年に北海道交通安全推進委員会の交通安全推進モデル団体に指定された。 同自治会は2年間にわたって「交通安全は家庭から」をキャッチフレーズに飲酒運転の追放、シートベルトの着用、夜光反射板の着用、正しい道路横断の励行などに努め、高い評価を受けた。 その後、自治会の交通安全部会は、全町的に輪が広がり、草の根の交通安全運動に一役買っている。 これに先立つ昭和51年、屯田市街地の婦人会も北海道交通安全推進委員会から交通安全運動推進婦人団体に指定され、やはり2年間でモデル的な実践を行い、成果を挙げた。 こうした地域的盛り上がりを背景に、全町的な交通安全町民大会や総決起大会も機会をとらえては開催された。 さらに、同54年(1979)には上富美、富美、札富美の地区住民が交通安全宣言大会を自主的に開き、事故防止への決意を示したのが注目される。 このほか昭和54年に上湧別町建設業協会が交通安全部会を設置するとともに、同59年(1984)には4の1に交通安全塔を建てて寄贈している。 このあと同63年(1988)に安全運転管理者を置いている町内の25事業所が、共同でチューリップ公園のそbに交通安全塔を寄贈し、ドライバーの目を引いている。 中湧別小学校は平成2年(1990)から毎年5月11日を「交通安全宣言の日」と設定、学校ぐるみで立ち上がった。 高齢化社会を迎え、お年寄りのドライバーが増える一方、輪禍に遭う事故も増加している。 このため昭和60年(1985)8月、遠軽警察署長と上湧別町交通安全推進委員会長連名委嘱のシルバー交通指導員制度を導入、平成8年(1996)度の場合は88人に委嘱状を交付している。 また、老人クラブに交通安全リーフレット、夜光反射材を配布している。 ユニークなのは福寿老人クラブが同元年(1989)から数年にわたって行った「交通安全目撃日誌」の試みである。 この日誌には街角の人や車の動きで交通安全上で気付いたことを何でも自由に書き込んでもらおうというもので、お年寄りらしい注意深い観察が、安全指導の資料として役立てられた。 交通安全施設の整備も年々進み、平成8年度には、町道交差点にはクロスマークを35ヶ所に標示している。 交通安全保護帽の着用 昭和58年(1983)5月16日午後5時23分ごろ、中湧別南町の国鉄名寄線10号踏切を自転車に乗って渡ろうとしていた塾帰りの中湧別小学校の男子児童が、通過列車にはねられて死亡した。 直接の死亡原因が頭部の打撲によるものであったため、犠牲となった児童が、もしヘルメットをかぶっていたら命はとりとめることができたのではないか、という声が事故直後に町民の間から高まった。 町内各小、中学校のPTAでも論議されて着用への気運が盛り上がり、連合PTA(安藤国夫会長)では、「児童・生徒交通事故防止対策会議」を数回開催し、対応を検討した。 この問題は、実は昭和56年(1981)12月の町議会で既に取り上げられ、町教育長も「 緊急課題として十分調査検討したい」と答弁していたが、結論を出すに至っていなかった。 このため町議会でも着用の早期実現を求める意見が相次ぎ、小学校では同58年10月から、中学校では翌59年(1984)4月から着用に踏み切った。 ヘルメットの購入については町が2分の1を助成した。 このあと、車にはねられた児童がヘルメットのお陰で大事故に至らず、その効果が実証された。 女性ドライバークラブ 屯市自治会女性ドライバークラブは、平成2年(1990)7月1日に発足した。 女性によるドライバークラブは、網走支庁管内では美幌町に続いて2番目であった。 毎年実施される遠軽地区交通安全協会上湧別支部主催の交通安全パレードに、屯市自治会の女性会員が個人的に参加、彩りを添えていた。 これらの人たちが中心となり、自治会内で運転免許証を持つ女性に働きかけ、クラブ結成にこぎつけた。 約120人の免許所有者全員が参加、初代会長に渡辺幸子が選ばれた。 2代松村真理子に続いて、3代吉田保子、現在は4代石田聖子に引き継がれている。 事業は、交通道徳の向上、会員相互の親睦などを通じ交通安全に寄与することを目的に、①交通道徳の普及宣伝、②交通法規、運転技能などの研修、③会員相互の親睦交流、などを進めることとしている。 具体的には夏や秋の交通安全運動における車両パレード、町主催交通安全街頭啓発活動、屯市自治会主催の交通安全街頭啓発活動などに参加している。 平成7年(1995)に、同クラブは屯田ふる里祭でのバザー売上金を町の交通安全活動に寄付した。 交通安全表彰 交通安全は、道路の機能を改善したり、安全施設設備を整備するなどのほか、国、地方公共団体や警察の指導、取り締まりの強化だけでは十分な効果が挙げられるとは限らない。 民間の安全運動推進団体やドライバーの協力があって初めて実効が期待できるのである。 交通事故防止のために、地位の先頭に立って活躍、大きな成果を残した交通安全功労者や団体、そして長年無事故、無違反を続けた優良運転者には、様々な顕彰制度があり、その功績をたたえ、労苦に感謝している。 顕彰を行っているのは地方公共団体、交通安全推進委員会などのほか、交通安全協会、安全運転管理者協議会、警察、内閣総理大臣など各種各級にわたっている。 また、民間の業界団体などが自主的に行っているものもあり、こうした顕彰制度が交通安全運動を下から支えているともいえる。 交通安全関係者の最高栄誉とされる緑十字章には胴章、銀章の受章者は町内からも数多く出ているが、金章となるtまだ2人しかいない。 志向の金章受章者は、遠軽地区交通安全協会元会長で前中湧別支部長の坂田直光である。 当時遠軽管内では初の受章であった。 坂田は昭和23年(1948)4月から遠軽地区交通指導員になったのを皮切りに、遠軽地区交通安全協会長(昭和51年~胴61年)、同協会中湧別支部長(昭和42年~平成8年)、運転免許更新時講習指導員(昭和46年~同63年)など数多くの役職を努めた。 砂利トラックの交通安全には、湧別川砂利協同組合の事務局長として人一倍努力してきた。 こうした業績が認められ、昭和62年(1987)1月21日、全日本交通安全協会長緑十字金章を受章した。 坂田は平成3年(1991)7月にも警察表彰で最高位の警察協力章(警察庁長官表彰)を受賞している。 これは北海道警察北見方面本部管内でも初めての受章であった。 もう一人の緑十字金章の受章者は、(株)横山サービスセンター会長の横山美治である。 平成5年(1993)1月14日、優良運転者として最高の栄誉に輝いた。 横山は当時で運転歴52年であった。 この間のトラック運転、マイカー運転を通じ無事故無違反を続けた。 さらに自分の会社の従業員にも無事故無違反、安全運転の指導を徹底したほか、交通安全協会に交通指導車を寄贈したり、自宅前の横断歩道に自費で交通安全看板を設置するなどの社会貢献を果たした。 町内の民間団体では、湧別川砂利協同組合が、昭和41年(1966)から優良運転者表彰を行うとともに、文書啓発指導、交通法規講習会の開催、組合独自のパトロール制の採用などで効果を挙げている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 交通災害共済制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿 革 網走支庁管内23町村によって、「地方自治法」に基づく一部事務組合である網走管内町村交通災害救済組合が、昭和43年(1968)に結成され、翌44年(1969)1月1日からこの共済制度が発足した。 町民一人当たり年額360円の会費を納めて加入すると、加入者が国内のどこで交通事故(汽車、電車、船舶、飛行機は除く)に遭っても、その被害程度(1等級~6等級)に応じて、50万円から2000円の見舞金を支給するという制度である。 その後、昭和50年(1975)、同56年(1981)と何度か会費や見舞金基準が改正され、現在は会費が500円にアップされたほか、等級も8段階に細分化し、死亡したときの1等級の見舞金を100万円、7日以下の治療期間を要する傷害を受けたときの8等級は2万円と改めている。 加入と支給の状況 昭和53年(1978)度以来、加入率が80%を超えている。 これまでの最高加入率は、平成8年(1996)度の84.5%であった。 加入者の実数は、人口の過疎化により減少傾向にある。 見舞金の支給は、件数で昭和56年(1981)度~同62年(1987)度、金額で同56年度~同63年(1988)度の期間が比較的多く、平成8年度は18件、163万円にとどまっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3章 topへ |
消 防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 遠軽地区広域組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿 革 地域の発展と交通網の整備に伴う生活圏の拡大が顕著になる一方で災害は複雑・多様化し、事故・急病などが年々増加した。 常備消防力の充実強化が、一層強く求められるようになったのである。 これらの課題を広域的に解決するため、昭和46年(1971)10月に遠軽地区消防組合が発足し、遠軽地区の遠軽町、上湧別町、丸瀬布町、白滝村、生田原町、佐呂間町の7町村で構成された。 消防本部と消防署は遠軽町に、消防支署は他の町村にそれぞれ設置され、7町村に消防団が配置された。 こうして現在のような消防署(支署)という常設の消防機関と、普段は職業を持ちながら非常時に消防活動に従事する消防団の組織ができ上がった。 この2つの消防機関が両輪となって、火災や各種災害からチュ民の生命と財産を守っている。 同組合の管轄区域は約2240平方㌔㍍で、人口約6万人を抱えている。 昭和46年(1971)に職員58人、団員923人、消防ポンプ自動車34台、小型動力ポンプ29台、防火水槽148基をもって業務を開始した。 平成9年(1997)4月1日現在では、職員126人、団員698人、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、山林工作車、積載車など合わせて39台、防火水槽248基のほか、救急車8台、指揮・広報車11台に増強されている。 この間、昭和59年(1984)に衛生・隔離病舎両組合を吸収合併して複合組合に改め、名称を遠軽地区広域組合としている。 ただし、隔離病舎部門は組合から分離して紋別地域に合併し、現在は消防と衛生の2部門が残っている。 上湧別支署 昭和46年(1971)の遠軽地区消防組合の設立に伴って発足した上湧別支署は、年ごとに消防体制を強化拡充した。 それまでは中湧別分団に常備団員1人が配置されていたが、上湧別支署になって消防職員4人に増員された。 その後も何度か増員し、同54年(1979)から支所長を含め4人の体制になっている。 中湧別には、分遣所がある。 機動力の増強、近代化にも努め、昭和52年(1977)から平成8年(1996)までの間に更新、または増車している。 現在、消防ポンプ自動車5台(うち水槽付2台)、小型動力ポンプ3台、指令車1台を購入、救急車1台を配備している。 これらは更新、または増車で充てられた。 また、昭和49年(1974)に消防無線局を開局、連絡通信の正確化とスピードアップを図った。 消防施設の整備も、目覚ましいほど進んだ。 消火栓は15基と変わらないが、防火水槽は平成7年(1995)度までに79基に整備されている。 これは昭和45年(1970)以降、各地区にあった防火井戸の地下水位低下によりその機能を果たせなくなってきたためである。 防火水槽の整備は同49年度から進められ、水利基準に適合した40㌧級のものを計画的に配置してきた。 支署の新庁舎は、昭和62年(1987)9月に完成した。 町役場庁舎と併せて、その南側に建て替えた。 鉄筋コンクリート平屋建て、約485平方㍍の広さで総事業費は1億3740万円である。 訓練塔を兼ねた昇降装置付ホース乾燥塔、昇降式ホース収納棚、訓練副塔、車両排気設備、車庫床暖房を備え、事務室、資機材庫などのほか上湧別町消防団のための団長室、団員控室、更衣室なども併置した。 上湧別支署中湧別分遣所の新築移転 中湧別地区の消防力を強化するため、老巧化し手狭になった中湧別分遣所を従来の中湧別南町から中湧別中町に移転新築した。 新文献署は、地域住民の生活と密接な関係がある消防団活動を円滑に進めることを目的に、コミュニティ機能を備えた”コミュニティ消防センター”という性格を有している。 総工事費2億1092万円をかけ平成8年(1996)6月25日に着工、同年12月に完成、同月から供用を開始した。 鉄筋コンクリート2階建て、延537平方㍍の広さである。 1階は消防車2台分の車庫やシンボル的な塔となるホース乾燥室をはじめ消防団事務室、会議室が配置されている。 事務室と車庫を結ぶ通路は、緊急時のスムーズな出動を考慮してスロープを施し、また事務室は消防車の出動に支障がないよう、常に車庫面を見通せる位置に設けている。 2階は90閉鋪王㍍の広さの集会室や20畳の和式談話室、吹き抜けのロビー、給湯室などを備え、地域住民利用に開放されている。 この新築移転に伴い老巧化した消防ポンプ車も更新し、水槽付ポンプ車1台を導入するとともに、消防無線機(移動局10W1台、携帯局5W2台)を整備した。 さらに分遣所から遠くなりサイレンが聞こえにくくなる地域をカバーするため、最新のサイレン遠隔吹鳴装置を新たに設置し、防災通信体制の充実を図った。 火災発生状況 産業や生活文化がますます発展し、生活様式の多様化が一層進んだ。 このため電気製品をはじめ石油、ガスなどの危険物を使用する生活が一般的となり、火災が増加し、さらに死者や負傷者を伴う火災の危険性は高まる一方である。 昭和50年(1975)から平成8年(1996)までの22年間に発生した火災は合計110件で、1年平均5件である。 1件も火災が発生しなかったのは、同2年(1990)のたった1年だけで、最も多かったのは、昭和55年(1980)の10件である。 また、22年間の死者は7人、負傷者は15人で、総体の損害は2億5783万円に及んでいる。 幸い昔のような大火はなかった。 車両火災は平成元年(1989)以降やや増える傾向にあり、同4年(1992)と同6年(1994)に2件発生した。 林野火災は昭和50年代に散発的に発生したが、同59年(1984)からはゼロを続けている。 この間、最も大きい林野火災は、同55年5月23日に0.6㌶(上富美)を焼失した事例である。 危険物施設と防火対象物 社会の進展や経済の発展などにより、町内の危険物施設や防火対象物は、徐々にではあるが増加している。 「消防法」の定めでは、危険物施設は、石油類など発火性、引火性の強い物品を製造、貯蔵したり、取り扱うところをいい、危険防止のため一定の制限を加えている。 主なものとしては屋外、屋内、地下、移動、簡易のタンク貯蔵所や屋内貯蔵所、給油所、一般取扱所がある。 また、「消防法」により指定される防火対象物は、万一出火すると危険が大きい不特定多数の人が出入りする施設や駐車場、倉庫などで、やはり防火・避難態勢や施設整備面で一定の認可条件が課せられている。 危険物施設の設置状況は、昭和57年(1982)に遠軽地区消防組合(のち遠軽地区広域組合に名称変更)管内では405件で、このうち上湧別町は59件(14.6%)であった。 これが平成元年(1989)に遠軽地区消防組合管内で403件とわずかに減少したが、上湧別町内では63件(15.6%)に増えた。 さらに同9年(1997)4月には同館内で428件、上湧別町内で64件(14.9%)となっている。 一方、指定防火対象物も増加傾向をたどっている。 昭和57年に遠軽地区消防組合管内で1062件、このうち上湧別町内で137件(12.9%)であったが、平成元年に同管内1130件、K町内149件(13.2%)、同9年4月に同館内1204件、K町内182件(15.1%)と年々増加している。 このような施設に対しては、火災や事故防止の各種運動などに合わせたキャンペーンや定期的な巡回立ち入り検査などを行い、問題のある点などの改善を求めたり、指導に努めている。 救急活動 消防業務の使命は、人命の救助である。 救急車による救急活動は、遠軽地区消防組合発足後、消防署を拠点として進めてきた。 上湧別町では昭和48年(1973)、渡辺組創立15周年記念として和湛辺正喜社長からセドリック48年型救急車の寄贈を受けてから、これを上湧別支署に配置し、より地域に密着した活動ができるようになった。 その後、同60年(1985)と平成6年(1994)に日本赤十字社からⅡB型救急車の貸与を受け、それぞれ更新している。 昭和50年(1975)から平成7年(1995)までの救急出動状況は、火災、自然災害、水難による出動はわずか14件で非常に少ない反面、交通やスポーツに伴う事故、労働災害が目立つようになった。 急病患者の搬送の増加も著しく、砂金は年間70~90件に達している。 全体の出動件数は年ごとに増え続け、同7年は179件を記録、11年前の昭和60年の141件に比べ約1.3倍となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 消防団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織と人員 上湧別町消防団本部の下に中湧別、上湧別、開盛の3分団が配置されている。 団員の定数は、人口過疎化の進行につれて減員されている。 昭和51年(1976)には137人であったが、同55年(1980)に118人、同58年(1993)に106人に改定され、現在に至っている。 平成9年(1997)4月現在の団員の配置は、団本部13人(うち女性団員10人)、中湧別分団39人、上湧別分団29人、開盛分団19人である。 機動力の配備は、中湧別分団(中湧別分遣所)に消防ポンプ自動車1台、水槽付消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ1台、上湧別分団に消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ1台、開盛分団に消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ1台。 このほか支署に水槽付消防ポンプ自動車1台と指令車1台、救急車1台が常備されている。 消防無線は、支署に基地・固定局を置き、各消防自動車の移動局やその他10台の携帯局と結んで緊急体制に備えている。 また、各分団に設置されている緊急伝達システム装置は、団員の招集や付近住民の避難命令をサイレンや放送で知らせるもので、装備近代化の一環として昭和62年(1987)、平成2年(1990)の両年度で整備された。 全道大会で準優勝 消防団の活動としては、春と秋の火災予防運動や歳末警戒時の啓蒙や査察、出初め式、春と秋の消防演習などがある。 このほか毎月の定期訓練も行い、ポンプ双方の技術などをみがいている。 遠軽地区連合消防演習は、広域組合加盟の7町村の持ち回りで毎年1回開催されている。 上湧別町では昭和52年(197)、同59年(1984)、平成2年(1990)、同9年(1997)に開かれた。 同年7月6日、チューリップ公園駐車場・文化センターTOM前広場で行われた第39回演習では、消防車両19台・指令車7台と団員498人、署員49人が参加した。 「消防精神の高揚と技術の錬磨」、「指揮統率、命令の徹底」、「消防団相互の連携強化」などを目的に、日ごろの訓練の成果を披露した。 平成3年(1991)、上湧別町消防団が日本消防協会から竿頭綬を受けた。 昭和50年(1975)に次ぐ栄誉である。 竿頭綬というのは、規律が厳正に保たれ、技能も優れていて、しかも消防施設が充実し、日ごろから使命達成のために努め、成績優秀な消防団に与えられる栄誉である。 また、平成5年(1993)8月、江別市で開催された北海道消防操法訓練大会の「小型ポンプ操法の部」に出場州他上湧別町消防団は、1年以上にわたる猛訓練の成果を十分に発揮して見事、準優勝に輝いた。 出場隊員は、北村茂、吉田耕造、細川洋之、武田昌一の4人で、北村茂が隊長を務めた。 女性消防団員の誕生 消防団の新しい顔として平成5年(1993)4月1日から登場したのが女性団員である。 女性団員の登用は、優しく気配りの行き届く女性の特性を生かして、住民に密着したきめ細かな予消防活動を展開しようというもので、23歳から48歳まで(平均年齢35.2歳)の主婦を中心として10人が採用された。 役割は、緊急時の後方支援のほか、お年寄り世帯、独居老人宅などに対する予防査察巡回や啓発活動で、その感性が役立つものと期待されている。 また、それまで男性だけで固いイメージの消防団に、さわやかな雰囲気を漂わせることになり、ソフトムード化に一役買っている。 団員不足と高齢化 消防団が抱える問題の一つは、団員のなり手が少なくて定員を満たすことができないことと、団員の高齢化である。 いずれも全国、全道的な傾向であり、将来に不安を残している。 社会の仕組みの複雑化や価値観の変化などに伴う自衛消防意識の低下が原因である。 上湧別町消防団においては、ここ数年定員を満たす団員数が確保できず、慢性的な団員不足の状態である。 平成9年(1997)4月現在では定数より6人少ない100人にとどまっている。 特に若年層の入団希望者がほとんどみられないことが、団員の高齢化にもつながっている。 団員の平均年齢は平成9年4月1日現在で、約39.55歳に達している。 同5年(1993)に平均年齢35.2歳という女性団員が入団したため、若干低下したとはいえ、昭和63年(1988)4月1日の38.08歳に比べ1.47歳もアップしている。 既に半数以上が40歳を超えている。 しかし、上湧別町消防団は、災害出動、演習、訓練、警戒、査察、点検など毎年80回前後出動している。 平成8年(1996)の出動は100回に及び、延べ出動人員も2177人を数えている。 火防団 地域集落の自衛のために組織されている自治会独自の火防団は、現在も南兵村一区、南兵村二区、南兵村三区、富美、上富美で存置され、活躍している。 しかし、長い歴史を持つ火防団も、町の自治消防体制の確立に伴い、その役割を終え解散したところもある。 旭、5の3,5の1などが既に姿を消しているが、残る5つの火防団は、町や消防支署の指導を受けながら、火災や水害などに出動するとともに、防災意識の高揚に努めている。 それぞれの火防団には、動力ポンプ1台が配置されている。 町は、自治会などが消防施設を設置したり拐取する場合に、その経費に対して一定の費用を助成している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 topへ |
災害と防災 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 防災体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防災会議 昭和37年(1962)施行の「災害対策基本法」に基づいて、翌38年(1963)に設置された上湧別町防災会議は、毎年1回会議を開き、災害情報の収集、機関相互間の連絡調整、地域防災計画の点検などを行っている。 会長(町長)と委員29人で構成している。 災害発生時に備えて設置されている災害対策本部は、平成4年(1992)の2度にわたる台風被害に対して、消防本部、消防団に出動を要請するなど非常配備を行い、被害を最小限度にとどめる対策を講じた。 上湧別町は幸い地震などの災害は少ないが、台風や集中豪雨、強風による被害がたびたび発生している。 これらの被害をできるだけ小さく食い止めるには、正しい情報をより早く知り、避難を含めた万全の備えをしておくことが大切である。 上湧別町地域防災計画では、災害情報報告伝達系統を確立するとともに、避難場所を設定するなど、万一に対応している。 水防協議会 「水防法」の規定により、上湧別町水簿王家威嚇の策定や水防に関する重要事項を調査、審議するため昭和62年(1987)に上湧別町水防協議会が設置された。 会長(町長)と委員25人以内で構成し、河川の洪水などの水害に備えて水防本部を設置している。 防災会議の災害対策本部と一体となって活動に当たるが、重要水防区域として湧別川右岸14号線地先(延長300㍍)、湧別川左岸16号線~上湧別橋(延長1100㍍)、の2ヶ所を指定している。 また、湧別川の遠軽町字川向、上湧別町字開盛、上湧別町字中湧別の3ヶ所にある網走開発建設部網走西部河川事業所管轄の水位観測所で常時水位を観察して、万一に備えている。 林野火災予消防対策協議会 近年、観光開発、道路交通網の発達、レジャー人口の増加などにより森林利用が多様化している。 このため、林野火災の危険性は高まっている。 林野火災予消防対策協議会は、上湧別町、上湧別町森林組合、森林愛護組合、町有林巡視人、遠軽地区林業指導事務所、遠軽営林署、遠軽地区広域組合上湧別支署、上湧別消防団、火防団、警察官駐在所、自治会、上湧別町農業協同組合、上湧別町教育委員会、小学・中学・高等学校、上湧別町観光協会、上湧別町建設業協会、陸上自衛隊第25普通科連隊、網走支庁、林業関係企業の代表で構成、町長が会長を務めている。 林野火災が心配される期間を危険期間(4月20日~6月30日)、予防強調期間(4月20日~6月10日)、無煙期間(5月10日~5月31日)と設定、町内関係機関が一丸となって毎年、林野火災予消防運動を展開している。 この期間、広報車、標語、ポスターによる警防思想の普及宣伝、入林者に対する携帯用灰皿などの指導、林野の巡視、火入れの安全対策の徹底などの活動を行っている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 治 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水害と治水対策 上湧別町内を流れる河川は大小合わせて29となる。 1級河川の湧別川水系を本流として、これに合流する1次支流1級河川の中土場川、富美川、ヌッポコマナイ川と2次、3次支流の普通河川がある。 これらの河川は、開拓時代から豪雨や融雪によって幾度となく増水氾濫を繰り返し、農地や橋、道路、住宅に被害をもたらしてきた。 人命をも犠牲にする悲惨な被害もあり、治水への期待は常に大きかった。 しかし、治水対策は遅々として進まず、ようやく戦後の昭和26年(1951)以降、主要河川を中心に着手、その後逐次改修整備が行われた。 このため国や道が管理する1級、2級の河川については、上湧別町内において水害に見舞われることは少なくなったが、普通河川は国営・道営の農業基盤整備事業などにより改修工事の手が加えられ整備されているが、いまだ原始河川状態のところも残されていて、早急な改修整備が待たれている。 平成4年(には、2度のわたり台風による大きな被害を受けている。 まず同年8月9日、台風10号崩れの低気圧が北海道を通過したのに伴い短時間に集中豪雨が襲い、同日午後9時35分ごろ湧別川の水位が危険な状態に達し、その後も増水が続いたため朝日地区や東町地区など4ヶ所で浸水が始まった。 町は直ちに対策本部を設置して、排水活動などを行い被害を最小限にとどめたが、牛舎浸水4戸、農作物冠水9.8㌶などの農業被害(被害額400万2000円)、河川4ヶ所、道路9ヶ所、橋梁2ヶ所、町道1ヶ所が欠壊するなどの土木被害(被害額1182万9000円)が出た。 この年の9月11日から12日にかけては、さらに大きな被害に見舞われた。 北海道東部を通過した台風17号は、8月9日を上回る集中豪雨をもたらした。 各地域の小河川が氾濫、最初は地域の火防団が応急措置をしていたが、それでも被害が拡大しつつあったので、対策本部は消防本部に出動を要請し、浸水家屋の排水活動を行った。 河川増水による家屋浸水、農作物の流失、浸水などの被害のほか崖崩れなども発生、わずか1ヶ月ほどの間に2度の災害を受けた町民は、いまさらながら自然災害の恐ろしさをかみしめた。 牛舎などの浸水家屋15戸(うち床上浸水1戸)、農作物被害202戸・1261㌶(被害額7億73万8000円)、河川(13河川19ヶ所)、道路(16路線32ヶ所)、林道(1路線2ヶ所)、灌漑溝(1ヶ所)の土木被害(被害額1593万4000円)が報告された。 治水対策が進んだといっても、自然の猛威の前には万全ということはあり得ない。 改めて全般的な防災体制整備の重要性が認識されるようになった。 湧別川の改修事業 湧別川に本格的な治水工事の手が入ったのは、昭和7年(1932)の大水害が契機となってのことである。 2年後の同9年(1934)に改修工事に着手した。 このあといったん中断されたが、昭和32年(1957)度に湧別川改修全体計画が策定され、同35年(1960)の第1次治水5ヶ年計画(富美左岸築堤工事等に着手)から第2次(上湧別右岸築堤工事等)、第3次(遠軽右岸築堤工事等に着手)、第4次(遠軽橋下流岩盤掘削工事等に着手)、第5次(湧別左岸築堤嵩上げ工事等)、第6次(湧別左岸5号樋門改築工事等)、第7次(上湧別右岸築堤嵩上げ工事等に着手)、第8次(遠軽右岸低水護岸工事等)にわたり5ヶ年計画を進めてきている。 また、平成9年(1997)から同13年(2001)までの第9次(河口部の改修等)が進行中であり、現在では上湧別町の流域においてはhぼ安心できる状態になっている。 中土場川改修工事の完成 中土場川は、1級河川湧別川下流部に合流する緩流河川である。湧別町、上湧別町、遠軽町の町界にある標高418㍍の山麓がその源となっている。 延長13㌔㍍の中小河川だが、改修の手が加わっていない原始河川であったため、融雪期や豪雨時にはたびたび氾濫を繰り返す”暴れ川”であった。 昭和41年(1966)6月にも、大きな被害を出している。 このため、地域住民から流域全体の改修を求める声が強く出されていた。 昭和40年(1965)に2級河川、同44年(1969)に1級河川の指定を受けたのを機に、改修要望の気運がされに高まり、北海道は同46年(1971)度から改修工事に着手した。 山側の灌漑用水路に沿って9.433㌔㍍の新水路を掘削、支流のヌッポコマナイ川368㍍を切り替えた。 さらに、延長11㌔㍍の築堤、16㌔㍍の護岸や道路橋14,鉄道橋1,水路橋2などの付帯工事も行い、18年の歳月と総工事費約47億3000万円の巨費をかけた工事が昭和63年(1988)11月に完了した。 流域面積は約43.2平方㌔㍍に及び、このうち4.2平方㌔㍍が氾濫の被害から解放されて、耕地として生き返った。 湧別川支流1級河川の富美川でも、昭和63年以降掘削工、護岸工が実施されており、平成8年(1996)までに延2780㍍を完了、水害に強い河川に生まれ変わりつつある。 網走開発建設部網走西部河川事業所 昭和26年(1951)、北海道開発局設置とともに、網走開発建設部湧別川上湧別改修事業所が中湧別に開設された。 同所は堤防がない地区の築堤と河道安定を図るための護岸、内水処理などを行う一方、概設堤防の除草、高水敷区間の切り開き、樋門操作、河川巡視などの維持管理に当たった。 昭和59年(1984)4月から、上湧別河川事業所と改称したが、同63年(1988)4月から網走開発建設部渚滑河川事業所を統合、新しく網走開発建設部網走西部河川事業所として再スタートした。 事務所を中湧別に置き、湧別川と渚滑川の管理に当たっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 治 山 平成4年(1992)の台風17号被害で一部に山崩れが発生したが、幸い町内では山崩れなどによる災害は少ない。 しかし、土砂の流出の恐れがあるところなどはあらかじめ保安林を設けたり、樹木の植栽、芝張りなどで災害防止に努めている。 保安林については、道営小規模治山事業(道単独事業)として平成5年(1993)度に上富美919番の1.5㌶、翌6年(1994)度に開盛714番の1.1㌶を指定している。 いずれも民有林だが、南兵村一区(4の1)の国有林253.52㌶も保安林に設定している。 町内の名勝地、五鹿山公園内の山腹の一部に、崩壊して土砂が流出する危険ヶ所があるため、昭和60年(1985)から平成6年にかけて治山事業を行った。 危険な山腹斜面に土砂流出防止の土留め工事と早期緑化を図るための芝張りと植栽を施し、第1期、第2期工事合わせて5434万3000円を投入した。 樹木の植栽は264本となった。 平成7年(1995)度からは、開盛公園内の小規模治山事業を実施してる。 池に流れ込んでいる渓流上部の不安定土砂の流出を防止、川の勾配を緩和するなどして園外への土砂の流れ込みを未然に防ぐことを目的としている。 平成7年(1995)度からは、開盛公園内の小規模治山事業を実施している。 池に流れ込んでいる渓流上部の不安定土砂の流出を防止、川の勾配を緩和するなどして園内への土砂の流れ込みを未然に防ぐことを目的としている。 道9年(1997)までに3000万円を投ずる計画である |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10編 | 地域活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 topへ |
住民活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 地域づくり助成事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域づくり振興助成事業 自治会や老人クラブなどの地域組織が、連帯感に基づいた自治意識を盛り上げ、心のかよいあう温かな地域づくりを進めることを目的に、町独自の制度として昭和56年(1981)5月1日に「地域づくり振興助成事業補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)が執行された。 ここでいう地域組織とは自治会、老人クラブのほか交通安全協会支部、防犯協会支部、身体障害者分会、母子会、小中学校PTA、青年団体、婦人団体、青少年指導センター、子ども会、スポーツ少年団、ボウイスカウト、文化団体、体育団体、商工団体、勤労者団体である。 補助金の対象となる事業は、①生活環境の整備に関すること、②生活上の安全確保に関すること、③レクリエーション施設の整備に関すること、となっている。 要綱は、これまで何度か改正されて現在に至っている。 補助の実績 要綱施行初年度の昭和5年(1981)度は、ごみ焼却炉が(16基)、札富美自治会の花壇設置(1ヶ所)、5の1自治会と4の1自治会の公園内遊具設備(各1式)の4件に、合わせて66万3000円の補助金が交付された。 自分たちが住み、活動する身近な地域や団体において、自らの手で住み良い環境づくりが行政の補助のもとで実行できるとあって、町民の関心は高く、次年度以降もこの制度の活用が相次いだ。 補助を受けた事業主体は、主として自治会である。 事業内容としては、ギミステーションや防犯灯の設置など生活環境、安全施設の整備に関する件数が圧倒的に多く、公園施設整備、バス待合所設置などの活用も多い。 これらの事業の中で、補助額が最も大きいのが自治会の会館の増改築である。 増改築だけみると、昭和57年(1982)度から平成8年(1996)度までの間に延べ12件、4266万2000円が交付され、全体の約3分の1を占めている。 平成8年度までの15年間に対象となった事業は、延べ392件で、補助金の交付額も1億2035まん2000円に達している。 1年平均では26.1件、約30万7000円となっている。 集会所の整備 集会所は、各種集会、打ち合わせ、憩いの場、懇親の場として欠かせない施設で、自治会活動の拠点となっている。 活用しているのは自治会のほか農事組合、婦人部、子ども会、老人クラブ、各班などであり、冠婚葬祭に利用される場合もある。 要綱では、これらの施設が老巧化したり、手狭になったとき、その増改築、補修、維持管理に対しても補助金を交付している。 補助率は、初め事業費の2分の1以内であったが、やがて3分の2以内に改善され、現在は4分の3以内になっている。 その補助を受け手建設し、維持・管理している集会所は次のとおりである。 集会所(要綱対象)
国および北海道の補助事業により建設され、その管理を自治会に委託している集会所は、次のとおりである。 集会所(国および北海道の補助事業対象)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 住民運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コミュニティ活動 自治省のモデル・コミュニティ施策が昭和46年(1971)度にスタートした。 この構想は、住民が新しい地域的な連帯意識のもとに、安全で快適な日常生活が営めるような近隣社会(コミュニティ)の形成を促進しようというもので、1970年団(昭和45年~)における地方行政の大きな課題であった。 自治省としては初年度に各都道府県に1ヶ所ずつモデル地区を指定する方針で、北海道からは深川市納内地区が第1号に選ばれた。 しかし、この構想を新しいまつdくりの根幹として重視した北海道も独自で取り上げ、上湧別町中湧別地区ただ1ヶ所をモデル・コミュニティ地区に指定した。 この指定に基づき組織づくりが進められ、中湧別地区コミュニティ協議会が昭和46年12月に設立された。 地区は旭、5の3,北町、中町、南町、東町、中鉄(中湧別鉄道自治会)、5の1の8自治会で構成、①生活環境を整え、明るい生活を営みましょう、②教養を高め、温かい人間関係をつくりましょう、③スポーツに親しみ、健康の増進に努めましょう、④交通道徳を守り、交通事故をなくすよう努めましょう、⑤心のふれ合うコミュニティづくりを進めましょう、⑥省資源、省エネルギー運動を進めましょう、をコミュニティプランとして掲げた。 協議会には環境、体育、青少年、社会などの各部会が設けられ、プランにのっとって花いっぱい、一斉清掃、ゴミゼロ、あいさつ、青少年健全育成、歩け歩け、交通安全、地域づくり、省資源などの各種運動に取り組んでいる。 昭和53年(1978)12月には地域住民による自主的な組織として上湧別地区コミュニティ協議会が発足、4の1,4の2,4の3,屯市、池内、札富美、富美、上富美、開盛の9自治会で構成した。 これにより全町にわたってコミュニティ活動が広がることになった。 現在は文化活動、青少年活動、スポーツ活動、生活環境、地域活動、広報活動の6振興部会とリンゴ並木管理部会を設け、積極的な活動を推進している。 なお、その後開盛は、上湧別地区から独立して活動している。 具体的な活動としては、年2回の古紙・空きびんの回収、子ども会リーダーの養成、各種清掃参加、花いっぱい運動の推進、神社公園にある藤棚の造成と管理、東山樹木公園の電飾点灯、リンゴ並木の管理と収穫などを行っている。 特に収穫したリンゴを「湧愛園」、小学校、保育所などに配り喜ばれている。 コミュニティづくりの主役はあくまでも権利と責任を自覚した住民一人ひとりといわれている。 それだけに地域住民の熱意が、この住民主体の活動を盛り上げる鍵となっている。 運動はその性格上、一朝一夕に成果を期待できるものではないが、着実に一歩一歩進んでいる。 新生活運動 毎日の生活から無理や無駄をなくしたい、と誰しも願いながら昔からの習慣や世間体から、なかなか実効できないものである。 生活の簡素化を全町的な運動として広げようと、昭和51年(1976)6月、上湧別町新生活運動推進協議会が結成された。 町が音頭を取り、自治会、農協婦人部、連合婦人会、町労働組合(地区労)、老人クラブなどのほか各事業所に呼びかけた。 同協議会は、会合などの時間厳守の励行をはじめ、結婚祝賀会、葬儀、見舞い・祝い金について申し合わせた重点推進事項の徹底を図った。 結婚祝賀会については、会費制として会費は2000円以内、葬儀の香典は2000円以内、見舞い・祝い金は1000円以内というのが内容であった。 これらの金額は時代の推移とともに改定され、平成9年(1997)度現在、結婚祝賀会会費4500円以内、香典と見舞い・祝い金がいずれも3000円以内となっている。 重点推進事項の実施状況は全般に必ずしも十分とはいえない。 特に結婚祝賀会については徹底が難しく、町内施設で開催されたもののうち、新生活運動に沿って実施されたのは平成元年(1989)度が10件中2件、同2年(1990)度5件中1件、同3年(1991)度10件中2件、同4年(1992)度11件中5件、同5年(1993)度9件中2件、同6年(1994)度7件中4件、同7年(1995)度9件中6件、同8年(1996)度6件チュ3件であった。 葬儀については香典返しの廃止、弔花・生花の自粛などを中心に一定の簡素化が進み、評価されている。 同協議会は、独自につくった供花やのし袋を販売して、趣旨の浸透に一役買っている。 花いっぱい運動 人々の心をなごませる花づくりは、明るい住み良いまちを築くために欠かせない。 上湧別町の花づくりは、各地域に結成されている老人クラブから始まったといっても過言ではない。 昭和49年(1974)には、町老人クラブ連合会、が全町的な花いっぱい運動を提唱した。 上湧別町寒地園芸営農センターなどの指導を受け、お年寄りたちがハウス造りから始め苗をそだてた。 翌昭和50年(1975)、老人クラブ連合会は、中湧別地区コミュニティ協議会と協力し、町内関係機関の協賛を得て役場、学校などの公共施設や市街地に234基のフラワーボックスを置いたほか、花苗を無償で配布し、全町的な花いっぱい運動の第1歩を踏み出した。 花いっぱい運動の推進母体は、花いっぱい運動推進会であるが、その運営は昭和47年(1972)に発足してから同49年までは老人クラブ連合会が中心だった。 同50年以降は組織も全町に広がり、同57年(1982)からは新しい規約も定められ、「町人に広く花を愛する心を植え付け、地域の環境美化運動を発展させ、明るく住みよい環境づくりを進める」という目的のため、①花いっぱい運動の普及、②花の育苗知識・栽培技術・研修・講習会の開催、などの事業を展開している。 平成8年(1996)度の事業では、チューリップ公園における育苗、国道242号沿いに200個のフラワーボックスの配置、花苗(9種22色、約4万株)の配布、先進地花壇視察などをおこなっている。 町民の化安心を集めている花壇コンクールは、昭和55年(1980)から始まった。 当初は老人クラブと学校、職場であったが、平成2年(1990)から個人も加わり、最優秀賞、優秀賞、努力賞、奨励賞を選んでいる。 毎年アゲラタム、インパチェンス、ベゴニア、サルビア、マリーゴールドなど約4万株の色とりどりの花が咲き競う花壇の美しさは、街に鮮やかなアクセントをつっけている。 札富美老人クラブが花壇コンクリートの始まった昭和55年以来平成8年まで最優秀賞9回・優秀賞7回の受賞は特筆すべきものである。 あいさつ運動 あいさつは、心豊かな人間関係を確立し、明るい家庭、楽しい職場、快適なまちづくりを進める基本ともいえる。 昭和55年(1980)に、町長を本部長とする上湧別町あいさつ運動推進本部が設置され、コミュニティ活動の一環として全町的な運動に着手した。 当初は運動月間を設け、ポスター・標語の募集、看板の設置、ステッカー・ポスターの配布・掲示、あいさつ道路の設置などによって趣旨の徹底を図ってきた。 あいさつ運動は、上湧別と中湧別の両市街地区とも西1条通りを指定、ここを通行する時に「おはよう」「こんにちは」「ありがとう」などのあいさつの励行を指導している。 「人と人の心をむすぶあいさつ運動を広げよう」をテーマに運動を進めている。 初夏(6月1日~6月10日)、秋(9月21日~9月30日)の交通安全運動に合わせた強調週間を設定し、期間中、西1条通りのあいさつ道路で毎朝30分間、街頭指導を行っている。 上湧別町自治会長連絡協議会 上湧別町自治会長連絡協議会は、平成2年(1990)4月、上湧別町内15の自治会の会長が集まり結成した。 同会は、相互の連絡を密にして親睦を図るとともに、自治会の自主的な活動を促進、共通の問題について研究協議を行い、その解決に努めることによって住民の福祉増進と地域振興に資することを目的としている。 毎年4月に総会を開催しているほか、10月には同連絡協議会の研修会を開き、地域における実践活動の在り方などについて研さんを深めている。 具体的な活動として、最も大きな成果を挙げているのが、町に対する各種要請運動である。 毎年12月に同連絡協議会として、町長に対し当面する地域の問題解決のため要望書を提出しているが、これまで街路灯・防犯灯の電気料金補助が2分のから3分の2に増額されたのをはじめ、古くなった防犯灯の器具取り換えが新設の場合と同様に新たに補助対象に加えられ、また、福祉バスが運行(月2回、第2・第4土曜日)されるようになった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 topへ |
集落の歴史と自治活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1節 | 旭自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治40年(1907)、湧別屯田第5中隊に所属していた篠野佐寿郎の弟、篠野光蔵が最初の鍬を下ろした。 篠野は、一帯が湧別兵村の公有財産地であることを知らなかった。 その後、屯田家族の遠藤鶴吉らが入地し、昭和5年(1930)ごろには通い作も含めて22戸になった。 公有財産地は、昭和7年(1932)、民有未開地として解放され、集落も39戸に達したので翌8年(1933)4月1日付で、旭として北兵村三区から独立した。 人口と戸数は、同5年ごろ約80人・22戸であったが、同22年(1947)ごろには200人を超え、57戸となった。 同35年(1960)に292人・55戸を数えたが、このころから離農が始まり人口減が続いた。 人口と戸数は、同40年(1965)189人・37戸、同45年(1970)128人・30戸、同50年(1975)81人・19戸、同55年(1980)74人・17戸、同60年(1985)68人・17戸、平成2年(1990)64人・13戸と下降線をたどり、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では58人・13戸となっている。 区域は、町内の最北端に位置する。 多少の起伏はあるが、おおむね平坦な土地である。 西北は湧別町川西、南は11号線、東は5の3(北兵村三区)が境になっている。 開拓以来、一貫して農業が主体の地域である。 昭和10年(1935)ごろには、薄荷栽培の全盛の時代もあったが、同40年代から酪農を導入、現在ではこれが主流となっている。 主な出来事 旭自治会開基五十周年記念式典が昭和58年(1983)11月24日、旭公民館で行われた。 自治会全員、佐々木町長、当時の開拓者や町議会議員ら多数が出席、先人たちの労苦をしのぶとともに、今後の地域発展を誓い合った。 表彰式、祝賀会は、会場を移して上湧別町社会福祉会館で開催された。 記念事業として、旭公民館敷地内に開拓碑を建立した。 昭和63年(1988)、老巧化した旭公民館(旧、旭小学校)を取り壊し、その跡に町が国の補助事業により集会施設の旭農業センターを建設した。 同年9月12日に旭自治会が盛大に落成祝賀会を催した。 同センターは、木造平屋建て78平方㍍で、総事業費は865万円であった。 平成4年(1992)には8月15日の2度にわたり豪雨に見舞われ、旭東の沢川が氾濫して、片岡幸雄所有の畠や牛舎が水浸しとなったが、町職員、消防団員、一般町民の協力により被害を最小限に食い止めた。 自治会年表(昭和51年以降)
自治会の活動 年中行事として実施しているものに旭神社祭、馬頭観世音供養祭、子ども会七夕祭りなどがある。 旭神社の例祭は、毎年9月21日で、上湧別神社の宮司を迎え、豊作、防災などを祈願している。 毎年7月17日の馬頭観世音供養祭では、僧侶を招き家畜の厄除けを祈っている。 子ども会七夕祭りは、毎年8月7日、旭農業センター敷地内で開かれている。 夜はキャンプをしながら花火を打ち上げ、各家庭から差し入れられたお菓子や果物を囲んで、思い出深い一夜を過ごす。 このほか、3月下旬に小学校新1年生の歓迎会、12月24日にクリスマス・イブの催しも開催している。 自治会が管理しているものは、旭農業センター(町が委託)、旭神社、旭開拓記念碑、馬頭観世音などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 佐藤吉一(昭和45年~同59年)、姉崎昭太郎(昭和60年~平成元年)、松岡武雄(同2年~同5年)、沢口満男(同6年~同8年)、片岡幸雄(同9年~現在) 【農業委員】 佐藤吉一、名取忠信、片岡幸義 【農協理事】 松岡武雄、片岡幸雄 【農事部長】 名取忠信、姉崎昭太郎、小川博一、松岡武雄、片岡幸義、楠瀬浩一 【農協婦人部支部長】 小川コハル、片岡京子、姉崎芳子、沢口敬子、楠瀬徹江、佐藤まさ子 【旭老人クラブ】 名取ツヨノ、佐藤吉一 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 5の3自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 5の3(北兵村三区)は、屯田兵が入地した由緒ある地域である。 明治30年(1897)に34戸、同31年(1898)に35戸が入り、北の守りを固める一方、開拓に従事した。 北は6号線から南は8号線まで、東5線から西3線までの区域で湧別町界に接している。 屯田兵解隊のあと、農村集落として発展した。 昭和50年(1975)以降、上杉製作所の工場建設、雪印乳業(株)社宅跡地に中湧別工業団地造成、セイコーマート高田中湧別店の進出、ホクレン農協スタンドゆうゆう給油所の開所、Aコープゆうゆう(現、ゆうゆう食事処)の開店などが続き、商工業の発展も目につくようになった。 さらに中川住宅団地に住宅新築がみられるなど、農村集落からの脱皮が振興している。 しかし、基幹産業の農業も、青年たちの手で経営規模拡大の努力が続けられている。 将来展望として、国鉄湧網線跡地道路の整備により、公営住宅の建設、商工団地の造成を進め、中湧別市街商工発展の起爆剤にしようという夢が描かれている。 戸数は、ほぼ横ばいだが、人口は、わずかながら減少傾向をたどっている。 人口と戸数は、昭和50年368人・100戸、同55年(1980)359人・96戸、同60年(1985)351人・102戸、平成2年(1990)343人・101戸、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では322人・99戸となっている。 主な出来事 5の3公民館の増築工事が、昭和59年(1984)7月に完了した。 これは2回目の増築で、床面積は174.9平方㍍となった。 事業費は、423万8000円(町補助金282万5000円、自治会寄付金141万3000円)である。 昭和8年(1933)に建設された神明宮拝殿は、年とともに老巧化が進み、改築の声が高まった。 当時の中川辰雄自治会長らの努力により、渡辺正明を建設委員長として改築事業が始まり、平成3年(1991)7月、新拝殿が完成した。 新国二三雄の250万円をはじめ、自治会以外の寄付金、自治会内寄付金150万4000円など、合計409万2000円が改築費に充てられた。 自治会年表(昭和51年以降)
自治会の活動 毎年夏に運動会か盆踊りを実施してきたが、平成6年(1994)から趣向を変え、催しの内容を充実した。 8月18日、文化センターTOMを会場に子供、大人、老人クラブ、婦人部の盆踊りのほか、民謡やマンボ踊り、カラオケ大会も加わって、多彩に繰り広げられ、200人以上の人たちが、夕方6時から10時ごろまで歌と踊りの一夜を楽しむ。 当日、5の3睦会老人クラブの例会と併せて、公民館を会場に物故者の供養を行っている。 5の3自治会と農事部が管理しているものは、5の3公民館と5の3グランドのほか、神明宮、馬頭観世音、地神、第5中隊三区兵屋の跡碑、北湧校仮校舎の跡碑などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 高橋尚一(昭和41年~同50年)、西潟明男(同51年~同55年)、伊藤昭夫(同56年~同62年)、中川辰雄(昭和63年~平成3年)、松浦光明(同4年)、小山新之助(同5年~平成9年) 【町議会議員】 高木喜六、室井利男、加藤政紀 【農業委員】 中川幸一、加藤政紀、松浦光明、高橋茂夫、中川菊夫、杉原顕治、藤井勇一 【農協理事】 松浦清、松浦光明、加藤政紀、中川菊夫 【農事部長】 原田信一、高橋茂夫、中川佳明、吉田哲司、加藤政紀、西潟治男、中川菊夫、杉原顕治 【農協婦人部支部長】 伊藤孝子、水野信子、大野よし子、松浦菊枝、小山好子、帯刀たえ子、松浦和子、月脚千恵子、中川永子、中川順子、加藤富士子、吉田勝江、杉原ツルコ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 東町自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治30,同31年(1897,1898)にわたり、第5中隊第2区隊の屯田60戸とその家族が、この地域に入地したのが始まりである。 地域内高台地は、農耕に適さなかったため、同36年(1903)の屯田兵解隊後は第二給与地であった現在の中湧別市街や他の痴呆に移住する者が多かった。 しかし、現在、屯田兵の家系で同地域にとどまっているのは2戸だけである。 大正5年(1916)、湧別線が開通したのを皮切りに名寄本線、湧網線が開通すると、中湧別駅が交通の分岐点として重要な役割を担うようになった。 その周辺に店舗、工場が次々と張り付き、人口も急増、市街地として発展した。 当時の5の2区は、集落と4つの町内会が複雑に入り組んでいたため、昭和44年(1969)に中湧別地区自治会の区域が再編成され、翌45年(1970)1月から現在の東町自治会が発足した。 東町自治会は、かって北兵村二区といわれた地域内の一部であり、8号線から11号線までの旧名寄本線跡地以東町界までが現在の区域となっている。 地域内には商店が1軒もなく、4事業所のみで、公営住宅(67戸)個人住宅が建ち並ぶ住宅地域である。 南町・北町・中町を含め農家はわずか12戸で、5の2農事部を結成している。 区域内には五鹿山公園、町営スキー場、パークゴルフ場、町営ゲートボール場があり、文化センターTOM、バスターミナル、役場出張所など公共施設に隣接している。 自治会発足当時の人口と戸数は、547人、151戸であったが、平成9年(1997)3月末の住民基本台帳では640人・239戸に増え、住宅地域となっている。 主な出来事 公営住宅「さくら団地」が昭和58年(1983)度から同62年(1987)度にかけて25戸が完成、公営住宅「つつじ団地」が平成元年(1989)度から同4年(1992)度にかけて24戸が完成、公営住宅「いちい団地」が同5年(1993)度から同7年(1995)度にかけて18戸が完成した。 農村地域は、一段と住宅地域に移っている。 昭和62年に湧網線、次いで名寄本線が廃止され、旧中湧別駅構内の跡地が大きく変貌した。 その跡地には、文化センターTOM、町営ゲートボール場、鉄道資料館、上湧別町開基百年広場と百年記念塔などが建設され、現在も再開発計画が進められ、その周辺は大きく変わりつつある。 自治会年表(昭和45年以降)
自治会の活動 自治会が全力で取り組んだのが、東町自治会館の建設運動である。 鉄道全線の廃止に伴い、その跡地利用を含めた中湧別再開発事業計画が策定されたが、これにより約20年間も地域活動の拠点として利用されてきた「寿の家」が撤去されることになった。 このため、自治会は、東町会館建設検討委員会を設置、アンケート調査の実施などを経て、その建設を決定し、平成5年(1993)6月13日に広さ84.24平方㍍の会館が落成した。 総事業費の900万円は、町補助金と篤志寄付、東町全戸の寄付によって賄われた。 自治会設立以来毎年続けていた運動会は、平成2年(1990)の二十周年を機に取りやめた。 最後の運動会には、国際交流事業の一環でアメリカから来日、当時役場に勤務していたイーストウッド・マイケルも参加、親善を深めた。 明るく住み良い地域づくりのため、自治会各組ごとに清掃責任区域を定め、クリーン上湧別町全町一斉清掃に併せて各組長を中心に清掃を実施、成果を挙げている。 自治会と農事部が管理しているものは、東町自治会館、5の2公園、屯田開拓顕彰碑、屯田兵集落跡碑、5中隊練兵場跡碑などの記念碑、馬頭観世音、町の保全樹木などである。 歴代自治会長他 (昭和45年~平成9年) 【自治会長】 沢口健蔵(昭和45年~同52年)、酒井孝(同53年~同60年)、高柳友五郎(同61年~現在) 【町議会議員】 佐々木克郎 【農業委員】 田中正、田沢栄雄、高柳友五郎、因芳民 【農協理事】 因芳民、沢口勝男、高桑義博 【農協監事】 高柳友五郎(昭和50年~同61年内代表監事)、高桑義博 【農事部長】 野村忠雄、員芳民、沢口勝男、高桑義博、田中正、高柳友五郎、沢口豊 【農協婦人部支部長】 大沼はな子、久保美智子、田沢佐和、加藤正子、因光子、高桑美惠 【東町寿(老人)クラブ会長】 高柳清治、酒井孝、大沼勝博 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 北町自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 北町自治会は、かって中町、南町、中鉄(中湧別鉄道自治会)とともに、中湧別自治会であった。 しかし、地域全体の人口が増加したため、昭和44年(1969)に再編成を行い、翌45年(1970)1月からそれぞれの自治会が再発足した。 地域は、9号線と中湧別3091番地の1交点から西に直進し、北は5の3自治会境界、東は東町自治会境界とする一円である。 地域内は大きく変貌している。 中核企業であった雪印乳業(株)中湧別工場が、昭和54年(1987)に閉鎖され興部工場へ吸収合併された。 その跡地の約半分が同56年(1981)、中湧別工業団地として生まれ変わった。 昭和62年(1987)に湧網線、平成元年(1989)に名寄本線が相次いで廃止され、住民に衝撃を与えた。 翌2年(1990)にはその鉄道跡地に町営バス車庫、町職員住宅などが建設された。 さらに、同年、網走開発建設部網走西部河川事業所跡地に北見トヨペット(株)トヨタピークル中湧別営業所、雪印乳業(株)跡地に北見日産自動車(株)中湧別店がそれぞれ新設開業した。 同3年(1991)にも工場新築が地域内で続き、活気を呈している。 人口と戸数は、1306人・427戸であった昭和53年(1978)がピークで、同60年(1985)は1207人・417戸、平成2年は1064人・401戸と次第に減り、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では1005人・411戸となっている。 主な出来事 子供の遊び場、地域住民のレクリエーションの場として、昭和50年(1975)に北町広場が開設された。 数々の功績を残し、昭和52年(1977)に町特別功労者第1号となった井上正志が、同59年(1984)に他界した。 雪印乳業(株)中湧別工場の撤退に当たっては、地元住民も強力な移転反対運動を展開した。 しかし、その熱意も実らず予定どおり興部町へ移転し、昭和54年(1979)には工場も解体され、完全に姿を消した。 平成8年(1996)4月に中湧別北町太陽の会(鈴木一憲会長)が、明るく開かれた生き甲斐のある地域づくりを目的として、設立された。 具体的な活動としては高齢者家庭の除雪、屋根の雪降ろし、独居高齢者への定期的訪問による声掛け運動、パークゴルフ等に招いてのレクリエーション等を行っている。 現在会員数は30数人である。 自治会年表(昭和45年以降)
自治会の活動 第1回自治会大運動会を昭和51年(1976)7月25日、北町広場で開いた。 同じ北町広場で同53年(1978)から仮装盆踊り大会も行っていたが、仮装盆踊り大会は、第5回(昭和57年)、大運動会は、うち2回の中止があったが、第11回(同63年)を最後に打ち切っている。 仮装盆踊りは一時、湧別、遠軽方面からの参加もあり、200人近い人の踊りの輪ができた。 自治会組織に婦人部、交通安全部、防犯部が新設されたのは、昭和55年(1980)のことである。 これで組織の充実強化が一挙に図られた。 自治会発足当時の組編成は10組であったが、その後、公営住宅などが増えたので、現在は15組に膨れあがっている。 自治会で管理しているものは、北町広場のほか忠魂碑、店舗発祥の地や徳弘農場の跡などの史跡などである。 歴代自治会長他 (昭和45年~平成9年) 【自治会長】 上杉藤雄(昭和45年~同50年)、宮口留蔵(同51年~同52年)、木村久(昭和53年~平成3年)、此下清一(同4年~現在) 【町議会議員】 立野信男、原昭二、因二夫、中津川稔 【中湧別長寿(老人)クラブ会長】 鈴木光左右衛門、小池正躬、池田賢蔵、田中嶬、西川照憲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 中町自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治36年(1903)、屯田兵第5中隊第二区隊が解隊した。 一般人として職業の自由を与えられた兵村民は、第二給与地がある現在の中湧別市街に移り、店舗を構える商人も多くみられた。 湧別線、名寄本線、湧網線の開通により、中湧別市街はその分岐点として、また、交通の要衛として発展した。 とりわけ中湧別駅前に位置する中町の発展は、目覚ましかった。 昭和45年(1970)、自治会の再編成により、中町自治会が発足した。 区域は北の9号線から南のヌッポコマナイ川まで、東は鉄道までであったが、鉄道廃止後は東3条通りまでとなった。 中湧別鉄道自治会(中鉄)は、国鉄各線の廃止で国鉄職員が地域を離れたため、自治会として機能しなくなり、徐々に中町、東町、南町各自治会に分割併合され、平成5年(1993)4月1日、完全に消滅した。 中町は、商業の中心地域として発展してきたが、まちの過疎化に伴い、いまひとつ活気が出ないのが現状である。 それでも焦点、飲食店が建ち並び、旅館、ハイヤー会社、郵便局、金融機関などが集中していて、ショッピングや歓楽の中心地になっている。 人口と戸数は、自治会が発足した昭和45年は625人・178戸であったが、同50年(1975)は532人・154戸、同55年(1980)は479人・147戸、平成2年(1990)は386人・134戸と次第に減り、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では309人・134戸と自治会発足当時に比べほぼ半減した。 主な出来事 地域内の最も大きな変化は、鉄道の廃止とそれに伴う跡地利用によるものであった。 湧網線(昭和62年)と名寄本線(平成元年)の廃止に伴い、中湧別駅と線路などの跡地利用がクローズアップされた。 その中心となったのが、多目的施設である文化センターTOMの建設である。 平成5年(1993)に図書館、マンゴ美術館、バスターミナルを併設してオープンした。 また、町役場の中湧別出張所、上湧別町商工会もTOM内に開設され、地域住民の利便性が高まった。 自治会年表(昭和54年以降)
自治会の活動 中町自治会の要望が実り昭和54年(1979)、農村公園(通称、きのこ公園)が中湧別駅横に完成した。 遊具、野外ステージ、ベンチなどが設置され、子供たちばかりでなく、一般町民からも親しまれてきたが、湧網線・名寄本線廃止に伴う周辺再開発事業により平成4年(1992)に取り壊された。 「憩いの家」横の青空広場も遊園地からゲートボール場へと変遷し、同5年(1993)には単身者公営住宅(チューピットハイツ)が建設されたので、姿を消した。 いずれも自治会が管理していたものである。 新しくできた文化センターTOMの周辺では、毎年各種行事が行われている。 広場は、平成6年(1994)から冬の一大イベント、湧別原野100kmクロスカントリースキー大会のゴールとなる。 夏には駅前通りから文化センターTOMまでを会場にして七夕祭りが行われ、本州から取り寄せた笹竹でにぎやかに飾り、楽しい歩行者天国として解放される。 同5年から秋の屯田ふるさとまつりが文化センターTOM周辺広場を会場として、盛大に開催されるなど、1年を通して町民の歓声が響く。 これら地元の行事は上湧別町商工会、上湧別町、中町自治会が一体となって実施している。 同8年(1996)8月4日には七夕祭が上湧別町開基百年記念事業として行われた「よさこいソーラン踊り」と共催された。 中町自治会にある史跡は、陸軍経営部と仮学校の跡、兵村工事作業場の跡などである。 歴代自治会長他 【自治会長】 宮川俊彦(昭和45年~同50年)、小池正躬(同51年~同54年)、三宅悟(昭和55年~平成5年)、坂本忠義(同6年~現在) 【町議会議員】 大滝敬二、手塚一、林新一、坂本堅弥 【中湧別福寿(老人)クラブ会長】 坂田直光 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6節 | 南町自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 昭和45年(1970)1月、中湧別自治会から新しく発足した南町自治会は、東は旧名寄本線、西は湧別川堤防、南は11号線、北は中町との境界を分けるヌッポコマナイ川に囲まれた地域である。 発足当時は420戸ほどあったが、核家族化の傾向があるにもかかわらず、鉄道各線の廃止の影響が大きく戸数は減り、平成2年(1990)に405戸、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では386戸まで落ち込んでいる。 昭和55年(1980)に1374人を数えた人口も、平成9年3月末には1000人台を割り、929人に減っている。 北町、中町と違い商店などは少ないが、上湧別町社会福祉会館、上湧別町総合体育館、両湧別学校給食センター、上湧別厚生病院をはじめ、警察官駐在所、網走開発建設部西部河川事業所などの公的な施設が集中している。 また、中湧別小学校、湧別高等学校、さくら保育所、みのり幼稚園など文教施設や建設会社を中心とした事業所が多いのも特徴である。 しかし、平成6年(1994)、NTT中湧別営業所が合理化のため廃止された。 主な出来事 北海道湧別高等学校の改築、中湧別小学校の改築、上湧別町総合体育館の新設、上湧別町農業協同組合中湧別支所店舗の新築など公的な施設の改築、新築が続いた。 このうち老巧化した湧別高等学校の校舎改築については、昭和51年(1976)に改築期成会が結成された。 ねばり強い要請活動が実り、同54年(1979)に調査設計費が認められ、翌55年(1980)に着工した。 新校舎は、同57年(1982)に完成したが、改築落成式は、開校三十周年記念式典と併せて同58年(1983)に行われた。 自治会年表(昭和45年以降)
自治会の活動 自治会発足翌年の昭和46年(1971)に初めて監事を置いたのに続いて、随時、部会を新設して自治会の運営、事業を充実させ、現座愛の組編成は15組である。 部会には子供育成会(昭和51年設置)、体育部、衛生部、交通安全部(同54年)、福祉部(平成3年)などがある。 自治会としては、各部会の事業を中心に活動している。 子供育成会は、自治会の助成のほか、年2回程度古新聞・空きびんの回収、毎年1月のしめ縄回収などにより事業費を確保、子供の一夜研修、七夕提灯行列、ウォークラリー大会、駅伝競走などの行事を行っている。 体育部は、ミニバレーボール、パークゴルフ大会の実施をはじめ、町内の各種大会に参加している。 衛生部は、春秋の一斉清掃に併せた河川清掃やクリーン上湧別事業推進など地域の環境衛生美化に取り組んでいる。 交通安全部は、毎年計画的に防犯灯に対する夜行性交通安全板取り付けを進め、、さらに、交通安全運動週間中などには部員が各種活動に積極的に参加、事故防止に努めている。 福祉部は、独居老人に対する声かけ運動を実施、異常を発見した場合はすぐに民生委員など関係機関に連絡がとれる体制をとっている。 また、独居老人、老夫婦世帯で冬の除雪が困難な場合は組で対応している。 さらに、年に1回、上湧別町「湧愛園」と湧別町「オホーツク園」の特養施設を慰問し、入園者に必需品などを贈っている。 歴代自治会長他 (昭和45年以降) 【自治会長】 村松康(昭和45年~同50年)、星幸男(同51年~同52年)、菊地信義(同53年)、小野寺幸男(同53年~同57年)、田中重一(昭和58年~平成3年)、頓西国一夫(同4年)、梨沢稔(同4年~同7年)、中川快(同8年~現在) 【町議会議員】 我妻嘉人、西山鴻治、田中正、頓西一夫、小野小寺幸男、渡辺正利、西川仁史、小池寿治 【中湧別南町喜楽(老人)クラブ会長】 村松康、星幸男、野村忠雄、小野寺幸男 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7節 | 5の1自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 5の1(北兵村一区)は、明治30,同31年(1897,1898)に入地した屯田兵(第4大隊第5中隊第一区隊)70戸によって開拓された。 大正10年(1921)、湧別川西19戸を分離して札富美を創設、昭和45年(1970)には自治会再編成により、一部を中湧別市街に編入して現在に至っている。 地域は町のほぼ中央にあり、東は山林に、西は湧別川に、南は15号線で屯田市街地に、北は11号線で南町自治会と東町自治会にそれぞれ接している。 肥沃で平坦な土地が多いところから開拓以来農業が盛んで、大正4年(1915)には140戸の集落となり、人口も約850人を数えた。 その後一部地域を札富美へ分割したことや、昭和30年代(1955~)からの離農増加で農家戸数は急激に減少した。 昭和50年(1975)以降の地域内人口と戸数は、同年506人・132戸、同5年(1980)598人・156戸、同60年(1985)644人・179戸、平成2年(1990)602人・188戸、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では559人・192戸dっw、農家戸数は減少しているが、一般家庭戸数は、増加に転じて住宅地域に移っている。 主な出来事 自治会の活動拠点である5の1会館は、昭和33年(1958)に一度改築されている。 しかし、その後30年以上経過し老巧化が再び目立つようになった。 このため、平成3年(1991)改築計画が決まり、同6年(1994)10月に着工、翌7年(1995)2月12日に落成した。 総事業費は1689万2000円、4分の3を町が補助、4分の1を自治会が負担した。 木造平屋建て、125.7平方㍍の広さで、内部は会議室2室のほか、台所も備えている。 自治会ばかりでなく、老人クラブ、婦人会、子ども会などの活動に幅広く利用されている。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 毎年1月の最終日曜日に自治会内対抗ミニバレーボール大会を催し親睦を深めている。 老人クラブが例年3月13日に開催する例会では、物故者の供養が行われている。 毎年6月、5の1会館、5の1公園などの清掃には自治会役員、各班の衛生係、班長が参加して実施し、また、8月には墓地の清掃を関係者で行っている。 自治会が管理しているものは、5の1会館、5の1公園のほか、開拓記念碑、屯田兵第5大隊第4、第5中隊本部跡などの碑や史跡である。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 黒川一郎(昭和41年~同54年)、工平恵造(昭和55年~平成3年)、三浦昭二(同4年~現在) 【町議会議員】 村上清司、渡辺正喜、(昭和41年~同50年までは4の1自治会に所属)、宮田勝弘(旧、中鉄自治会出身)、黒川毅一 【農業委員】 前川美夫、林功、藤井政幸、山田明 【農協理事】 工平恵造、中村行雄、田浦多三次郎、藤井勝治 【農協監事】 高柳良吉 【農事部長】 黒川一郎、工平恵造、藤井政幸、田浦多三次郎、佐野正幸、藤井勝治、山田明、森正美 【農協婦人部支部長】 三浦郁、中村ヒデ子、中川カヲル、山田みつ子、工藤エミ子、田浦和子 【東町寿(老人)クラブ会長】 藤井勇、黒川久蔵、横山仁三郎、村上藤七、庄田繁、浅井良美 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8節 | 屯市自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治30年(1897)の屯田兵入地と同時に、基線17号線(現、町役場付近)を中心に防風林地で囲まれた100区画の屯田市街地が設けられた。 この年、新潟県人の渡辺表太が上川の永山村から来住し、雑貨商を営んだのが、屯田商業の始まりである。 その後、浜頓別(現、湧別町)や道内各地から次々と商人がやって来て店を開いた。 また、同29年(1896)から屯田兵村建設工事に従事していた職人、木挽、運搬人などが、この屯田市街地に定着、たちまち、にぎわいをみせるようになった。 生活物資や木材運搬などで活気を呈し、明治45年(1912)ごろには料理店、旅館、運送店、その他の商店を合わせて40数軒が立ち並び、市街地に膨れあがっていた。 しかし、鉄道の開通によってその分岐点となった中湧別に物資輸送の拠点が移り、ややさびしくなった。 それでっも役場や学校、郵便局、警察などの官公庁が集まり、中心地としての役割を果たしてきた。 昭和40年(1965)、池内自治会が上湧別自治会(現、屯市自治会)から分離独立した。 同自治会はその6年前に佐呂間町から移ってきた池内工業(株)湧別工場の社宅、独身寮入居者で組織し、独自の活動を行っていた。 しかし、工場縮小に伴い同58年(1983)、再び屯市自治会と合併した。 地域は15号線と湧別川の交点より同川を上り、16号線と17号線の中間を左折して西1線に至り左折し、西1線と上湧別土地改良区灌漑溝第1支線との中間を右折して18号線に至り、さらに、同線をを左折し、灌漑溝第1支線に至り、これを右折して19号線に至り、同線を左折直進して湧別町界になる。 北は5の1自治会界とする一円である。 人口と戸数は、昭和50年(1975)154人・443戸、同55年(1980)1456人・439戸、同60年(1985)1458人・460戸、平成2年(1990)1313人・443戸、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では1223人・443戸と人口は減りつつあるが、一貫して15自治会中最多の住民を抱えている。 主な出来事 自治会は行政の中心地にあるので、上湧別町総合庁舎をはじめ特別養護老人ホーム「湧愛園」、農村環境改善センターなどの建物が地域内で次々と完成した。 このうち総合庁舎は役場庁舎とコミュニティセンター、消防庁舎も併設されている。 総合庁舎は昭和62年(1987)7月、消防庁舎は同年9月にそれぞれ完成、同年11月3日に盛大に落成祝賀会が行われた。 昭和53年(1978)、著名な画家である馬掘法眼喜孝画伯が、湧別屯田の屯田兵386人の肖像画を町へ寄贈した。 農村環境改善センターで、その除幕式を行ったあと、郷土資料館に展示し、現在は上湧別町ふるさと館JRYで一般に公開している。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 納涼盆踊り大会は、昭和63年(1988)から実施してきたが、平成5年(1993)に上湧別屯田夏まつりと名称を変更、内容をさらに充実させた。 上湧別町商工振興会、上湧別町農業協同組合、屯市自治会が町の助成を受けて共催し、毎年8月15日から6日間、農協整備工場の広場で開催している。 プログラムの中の盆踊り大会は 歴代自治会長他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9節 | 4の3自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治30,同31年(1897,1898)に64戸が屯田兵として入地したのが始まりである。 当時の南兵村三区(4の3)は、北は15号線から南は21号線の間、東は基線を境にして市街の宅地を除き、西は湧別川西18号以南富美小学校付近基点までの広大な地域であった。 明治43年(1910)、富美地区が南兵村三区から独立し、さらに、その後16号線から17号線までの間が屯田市街地に移された。 その結果、現在の区域は17号線から21号線間(4の2を除く)湧別川堤防から国道242号までである。 この区域には屯田兵のほか、一般移住者も次々と入植、発展の基礎を築いた。 明治から大正にかけて木材加工業が栄えたが、農業中心の区域だけに昭和36年(1961)ごろから農業経営の大型化、機械化に対応、町内最初の酪農共同経営と生活共同経営が試みられた。 しかし、効果があがらず同40年(1965)ごろ解散、個別経営に戻った。 最近は、秋まき小麦、玉葱、馬鈴薯、ビートの栽培を中心に農村地帯として発展している。 昭和50年(1975)以降の人口と戸数は、同年287人・64戸、同55年(1980)233人・53戸、同60年(1985)225人・52戸、平成2年(1990)243人・61戸、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では194人・53戸となっている。 主な出来事 4の3自治会史「星霜八十年」を昭和52年(1977)9月に発刊、先人たちの足跡をたどり遺徳をしのんだ足かけ6年をかけた労作であった。 同59年(1984)7月、4の3公民館の増改築工事が完成した。 既存部分を改築し、1室分増築したもので総面積は188.73平方㍍となった。 857万1000円の工事費は、町補助が574万2000円、自治会負担が282万9000円であった。 町内初の上湧別リバーサイドゴルフ場が昭和61年(1986)、17号線と21号線間の湧別川河川敷に完成した。 上湧別振興公社が造成管理しているもので、ゆったりとしたレイアウトでフラットの中にも細かな起伏のある18ホールのコースは、町内外のゴルフファンから親しまれている。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 毎年8月12日、明徳寿クラブ(老人クラブ)の例会と併せ、4の3公民館を会場に物故者供養祭を行っている。 祭壇を飾り僧侶を招いて、参加者全員が焼香、故人をしのび、冥福を祈っている。 自治会では8月15日に馬頭観世音の供養を行い、家畜の厄除けを祈願している。 八幡宮では元旦祭(1月1日)、豊穣祈願祭(4月25日)、例大祭(9月1日)、大祓祭(12月25日)を行い、上湧別神社の宮司が司祭し、自治会の人たちが参拝している。 神社境内、公民館などの日常的な星霜、草刈り、の作業も行っている。 現在も4の3火防団は、消防動力ポンプ1台を所有、10人余の団員によって定期的に整備点検して万一に備えている。 運営は町と自治会の補助金による。 自治会が管理しているものは、4の3公民館(ゲートボール場、グラウンド併設)、八幡宮をはじめ、第4中隊三区兵屋の跡、日露戦役記念碑などの史跡、碑など多数ある。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 国枝守(昭和47年~同50年)、斉藤正揮(同51年)、加藤幸美(同52年)、中西隆(同53年)、野田昭二(同54年)、福本正巳(同55年)、八巻貢(同56年)、菅野盛一(同57年)、長谷川繁雄(同58年)、馬場純男(同59年)、宮嶋初男(同60年)、松本栄(同61年)、高井恒(同62年)、片岡武寛(同63年)、野田寿幸(平成元年)、八巻志郎(同2年)、長谷川真治(同3年)、渡辺勇(同4年)、前川芳男(同5年)、武藤公司(同6年)、宍戸一文(同7年)、宮嶋寿憲(同8年)、渡辺昭男(同9年~現在) 【町議会議員】 八巻貢、片岡秋美 【農業委員】 片岡時雄、内田清、国枝守、片岡武寛、八巻貢、渡辺勇 【農協理事】 長谷川繁雄、八巻志郎 【農協監事】 内田清、八巻志郎 【農事部長】 宍戸正、野田昭二、福本正巳、菅野盛一、馬場純男、宮嶋初男、福島嘉三、大泉守、高井恒、片岡武寛、野田寿幸、長谷川真治、渡辺勇、前川芳男、塚本旻、武藤公司、宍戸一文、宮嶋寿憲、渡辺昭男、加藤英俊、片岡節夫、武藤俊美、国枝徹 【農協婦人部長】 浅井芳美 【農協婦人部支部長】 矢口芳、中西藤江、片岡はつ枝、国枝うめの、花木トヨ子、宍戸ミヨ子、馬場咲子、福本八重子、片岡トミ子、八巻成子、松本和子、高井良子、前川美代子、長谷川ひで子、渡辺ふみ子、武藤キク、渡辺厚子 【明徳寿(老人)クラブ会長】 片岡時雄、松本馨、菅野賢、中村明義、国枝守 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10節 | 4の2自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち この地区も屯田兵が草分けである。 明治30,同31年(1897,1898)に第4中隊二区の67戸、414人が入地した。 同36年(1903)には屯田兵が解隊された。 その後、南兵村二区、4の2町内会、南兵村二区と変遷をたどり、昭和37年(1962)に4の2自治会と改称され現在に至っている。 区域は、北が19号線を酒井に屯田市街地に接し、西は21号線湧別川の地点を堺に野3に隣接している。 また南は4の1,東は山地本嶺で湧別町と分けている。 純農村地域であり、昭和40年(1965)ごろから離農により戸数が減り始め、一時90戸前後あったが平成9年(1997)3月末の住民基本台帳では77戸に減り、人口も273人にとどまっている。 主な出来事 地域の歴史を後世に伝える4の2自治会史「拓湧の八十五年史」は、編集に7年の歳月をかけて昭和57年(1982)1月発刊された。 254頁に及ぶ貴重な記録である。 この年、4の2公民館の改築と天満宮神社鳥居の建設に向けて、自治会に建設委員会を設置、その翌年に公民館の増改築が決まった。 工事が完成し、落成式を行ったのは昭和61年(1986)2月15日である。 建物の床面積は284.44平方㍍で、2350万円の建設費には町補助金と自治会内寄付金が充てられた。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 南湧(老人)クラブは,毎年8月14日、4の2公民館で物故者供養祭を執り行っている。 翌15日には馬頭観世音の供養祭を実施、家畜の厄除け祈願をし、自治会からも多くの者が参加、供養している。 天満宮神社の祭典には元日祭(1月1日)、豊穣祈願祭(4月25日)、豊穣感謝祭・例大祭(10月25日)、大祓祭(12月25日)などがあるが、いずれも上湧別神社宮司が司祭し、自治会の人たちが参拝している。 このほか日常的に草刈り、清掃作業、12月下旬にはしめ縄作りの奉仕を行っている。 自治会が管理しているのものは、4の2公民館、第4中隊事業場跡、南湧小学校跡などの史跡、碑である。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 自治会長】 井上春一(昭和50年)、板垣隆(同51年)、池田孝嗣(同52年)、平野総一郎(同53年)、八巻敏一(同54年)、井上徳俊(同54年)、岡和田幸一(同55年~同57年)、池田隆喜(同58年)、沢崎武夫(同59年)、藤本光利(同60年)、大川悦郎(同61年)、坂田重盛(同62年)、川副力(同63年)、加茂光夫(平成元年~同2年)、城岡隆至(同3年~同4年)、加茂光夫(同5年~同6年)、高橋年一(同7年~同8年)、花木昇(同9年~現在) 【町議会議員】 井上徳俊、上松芳男、麻植平治、平野隆樹 【農業委員】 石田静夫、板垣隆、井上徳俊,岡和田幸一、池田隆喜、国枝均 【農協理事】 上松芳男、石田静夫 【農事部長】 池田孝嗣、平野総一郎、八巻敏一、池田隆喜,岡和田幸一、沢崎武夫、大川悦郎、城岡隆至、川副力、原田武志、花木昇、平野英一、国枝均,八巻英俊、佐藤長次郎、上松勲、菊地優、森谷重俊、鈴木勝義、鈴木義重、梶原秀喜、井上政徳、上松和博 【農協婦人部支部長】 石村ヨネ子、梶原ミツエ,池田花美、井上静子、岡和田リエ子、池田節津子、城岡セツ子、花木カヨ,原田貞子、松原榮子、ym喜惠子、佐藤イチ子、上松久美子 【4の2南湧(老人)クラブ会長】 平野毅、沢崎武信、城岡喜蔵、国枝清、柴山正一、天野健一郎、平野潔、森谷重房、八巻恒雄、鈴木勝夫、上松芳男 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11節 | 4の1自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 4の1は、かって南兵村一区といわれ、明治30,同31年(1897,1898)に第4中隊第1区隊の69戸が入地した。 同36年(1903)、兵村が解隊されたあと、屯田兵たちを頼って本州から来住する者も多く,開拓時代を支えた。 地域は,南が湧別川を堺として開盛と接し、北は基線22号線で4の2,東は中土場、南東山地は遠軽町界、西は湧別川を鋏み富美とされぞれ隣接している。 この地域は湧別川流域の平野の中にあり、農業地帯を形成している。 人口と戸数は、昭和50年(1975)243人・58戸、同55年(1980)236人・55戸、同60年(1985)200人・52戸、平成2年(1990)167人・46戸と減少傾向をたどり、同9年(1997)3月末の住民基本台帳では142人・44戸となっている。 主な出来事 郷土誌「拓魂八十年」(380頁、350部)を昭和55年(1980)9月に発刊した。 編集委員長は樋口雄幸が務め、発刊費用は160万円であった。 4の1会館が狭くなったため昭和60年(1985)老人室、控室、玄関、物置、便所などを増改築した。 68.73平方㍍広くなり、総面積は198.744平方㍍となった。 事業費876万9800円のうち、町費補助は584万6600円、自治会負担は292万3200円であった。 平成2年(1990)12月、4の1公園内に簡易屋内ゲートボール場が完成した。 鉄骨造り平屋建て272.16平方㍍の広さで,コートは横16㍍、縦10㍍である。 正規のものより少し狭いが,小上がりもあり休息できる。 総工事費は、721万円であった。 自治会年表(昭和51年以降)
自治会の活動 4の1会館の清掃と備品の確認は毎月2回婦人部が、また、敷地内の清掃、花壇の手入れは毎月1回共進福寿(老人)クラブが行っている。 4の1公園については,公園役員が梅園の剪定、防除、収穫、販売を担当、パークゴルフ場と屋内ゲートボール場はそれぞれの同好会が管理している。 毎年8月15日は,自治会の手によって相馬大明神の祭祀、馬頭観世音の供養が行われる。 川上神社の月並祭に当たる毎月17日、共進福寿(老人)クラブが同神社の清掃を行うほか、1月1日の新年祭と10月17日の例大祭は,自治会が祭祀を執り行っている。 物故者の供養は,毎年12月8日の共進福寿(老人)クラブの例会に併せて行い、故人の霊を慰めている。 自治会が管理しているものは,4の1会館、4の1公園、川上神社、有線放送施設をはじめ数多くの史跡、碑である。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 田島澄蔵(昭和50年)、穴田寿之(同51年)、吉村邦彦(同52年~同53年)、工藤武(同54年)、石田敏雄(同55年)、秦野哲男(同56年)、田島澄蔵(同57年)、阿部岩雄(同58年)、工藤武(同59年)、穴田寿之(同60年)、吉村邦彦(同61年~同62年)、工藤武(同63年)、遠藤清喜(平成元年~同2年)、牧野勝一(同3年~同4年)、三品勲(同5年~同6年)、遠藤盛幸(同7年~同8年)、穴田寿之(同9年~現在) 【町議会議員】 三品正吉、渡辺正喜(昭和50年以降は5の1自治会に所属)、穴田寿之、吉村邦彦、細川正美 【農業委員】 田島澄蔵、吉村邦彦、東海林武敏、三品勲 【農協理事】 秦野松寿、穴田寿之、吉村邦彦、牧野勝一、三品正幸 【農協監事】 穴田寿之 【農事部長】 吉村邦彦、工藤武、石田敏雄、秦野哲男、牧野勝一、三品勲、安本明雄、竹内東洋児、岡村恒雄、岡村勉、三品正幸、三品幸義 【農協婦人部支部長】 三品ユキ,松野サダ,工藤ハナ、田島徳子、秦野久子、阿部みち子、石田セツ子、吉村テル子、穴田千恵子、工藤桂子、東海林百合子、牧野ミキ子、三品美代子、竹内美恵子、安本近 【共進福寿(老人)クラブ会長】 遠藤清治、小島鈴松、遠藤正雄、牧野光一、樋口雄幸、安本明、阿部太 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12節 | 開盛自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 開盛地区の最初の永住者は、山形県人の山口長之助だが、いつ入地したのか定かではない。 サナブチ橋の上流で、15町歩(約15㌶)の原野を開拓していた。 次いで明治31年(1898)に南兵村一区に入地した第2次屯田兵のうち26戸が、開盛地区に第2給与地を与えられ、その翌年から開拓を進めた。 その結果、明治末期には耕地が160町歩(約160㌶)となり、入地も45戸に増えた。 大正2年(1913)には、兵村からの住民22戸と一般移住の26戸の計48戸になった。 このため、南兵村一区から分離して第18部落会から分離したので、開盛部落と改称、現在の開盛自治会の区域が定まった。 町内の南端に位置する開盛は、湧別川に沿って南北に長く、サナブチ川の流域を境に遠軽町と接している。 農業中心の地域だが、幾多の変遷を経て酪農に移行している。 人口と戸数は、上湧別の町政施行時(昭和28年)に1006人・152戸を数え,最高を示した。 その後は減少を続け、平成9年(1997)3月間つん住民基本台帳では448人・149戸に落ち込んでいる。 しかし、最近は遠軽町のベッドタウンとして新築住宅が目につき、人口・戸数ともに増加に転じつつある。 主な出来事 老巧化していた開盛小学校の木造校舎は,昭和58年(1983)12月に鉄筋コンクリート2階建てに生まれ変わり、翌59年(1984)1月22日、盛大に校舎落成記念式典が行われた。 総事業費は、2億9191万円であった。 開盛生活館も狭くて老巧化が進んできた。 このため平成元年(1989)に北海道の振興補助により開盛住民センターが新しく建設された。 総事業費は、8400万円であった。 大正4年(1915)11月、社名淵駅として開業した開盛駅は、平成元年4月、名寄本線廃止と同時にその歴史に終止符を打ち,翌2年(1990)4月には自治会住民が見守る中、駅舎が取り壊された。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 大正7年(1918)、住民の氏神として建立された光華神社の祭典は、毎年9月23日に行われ、五穀豊穣、諸災鎮護を祈願し,豊かな恵みに感謝している。 宵宮にはビアパーティー、本祭では子どものための金魚すくい、宝さがし、ヨーヨーつりなどの楽しい催しが組まれている。 農事部の収穫祭は、平成2年(1990)から毎年11月に開催、会場の開盛住民センターに農作物や果物を持ち寄り,料理を味わいながら豊穣の秋に感謝する。 婦人会による演芸も花を添える。 このほか馬頭観世音、子守地蔵尊、聖徳太子堂などの供養・祭事を自治会の手で執り行っている。 また、開盛寿(老人)クラブは毎年8月20日、物故者を供養している。 自治会が管理しているものは、開盛住民センター(町が委託)、光華神社などの施設のほか、開盛特別教授場仮教室の跡などの史跡、保全樹木の原始林、光華神社境内の北限の三本杉などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 山口長蔵(昭和29年~同50年)、井上正治(同51年~同55年)、山口宏幸(同56年~同57年)、吉田早一(同58年)、遠田隆一郎(同59年~同62年)、長谷川薫(昭和63年~平成元年)、平塚定夫(同2年~同6年)、堀下武敏(同7年~現在) 【町議会議員】 山口長蔵、吉田早一、山口宏幸、平塚定夫 【農業委員】 吉田早一、堀下武、山口宏幸、中村貢、谷本八州男、斉藤勝利 【農協理事】 堀下武、中村貢、堀下武敏 【農協監事】 谷本八州男 【農事部長】 加茂秀雄、滝田尚正、井上照夫、木村博、井上政雄、中橋進、堀下武敏、斉藤勝利、谷本八州男、中村貢、山口啓司、小倉武 【農協婦人部支部長】 加茂オキク,吉田竹子、山口房子、小倉ケイ、井上久子、井上みつ、加茂キクコ、中村浪子、井上洋子、中村浪子、木村照子、松本勝子、堀下クニ子、山口幸子、秋葉キミ子 【婦人部長】 遠田チエ,佐野敬子、遠田涼子 【開盛寿(老人)クラブ会長】 及川隆見,石垣義治、山口長蔵、山口重雄、平塚定夫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13節 | 富美自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち 明治30年代(1897~)の富美地区は、兵村公有財産地があって南兵村三区に含まれていた。 その奥地は国有未開地であったので、公有財産地を小作する兵村民の一部が通い作をしていた。 富美開拓は,同39年(1906)、三井作次郎が国有未開地に入植したのを初めとしている。 次いで同41年(1908)、道庁の区画測量実施、翌42年(1909)の植民地開放告示によって開拓に加速がつき、大正4年(1915)ごろには34戸に増えた。 明治43年(1910)、南兵村三区から分離独立して富美が誕生、その後、大正9年(1920)に上富美地区を分割したので,現在の富美の区域が確定した。 区域は,富美南の沢上流の分水嶺(280.3㍍)より北に稜線をたどり、富美5号線と基線との交点に達し,左折して同基線を上り、紋別市界に達し、湧別町との界を経て札富美・4の3・4の2・4の1・開盛の各自治会を境とする一円である。 農村地域として発展著しく、昭和29年(1954)ごろは153戸に増加、人口も973人となった。 その後、離農者が続出して過疎化が進み、人口と戸数は、同50年(1975)には267人・69戸と激減、平成9年(1997)3月末の住民基本台帳では448人・149戸20人・50戸となっている。 しかし、町内の主要な酪農地帯となっている。 特筆されるのは、酪農業の本多正雄が上湧別町出身唯一の北海道議会議員として富美地区から出ていることである。 戦後初の昭和22年(1947)の選挙で当選、1期4年努めている。 主な出来事 昭和53年(1978)12月、富美開拓七十周年記念式典・祝賀会が富美小学校で行われた。 これに先立ち富美開拓記念碑が同校校庭に建立された。 また2年後の同55年(1980)7月、記念誌「拓いて七十年」が刊行された。 待望の富美地区住民センターは,北海道の振興補助により昭和59年(1984)12月完成、翌60年(1985)1月16日に記念式典・祝賀会が催された。 建物は木造一部軽量鉄骨平屋建て、473.7平方㍍の広さで、総事業費に7650万円をかけた。 老巧化著しかった富美神社を昭和61年(1986)に改築、奉祝祭と落成式を行っている。 富美小学校の老巧校舎改築は、平成元年(1989)11月末に完成、鉄筋コンクリートの校舎と鉄筋鉄骨中間構造の屋内体育館で総事業費は3億2294万円であった。 落成記念式典は、翌2年(1990)1月28日に行われた。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 自治会住民全員参加の親睦会は,昭和60年(1985)から毎年4月に開催されている。 毎年6月から8月にかけて1~2回実施している一斉清掃にも、ほぼ全戸が参加し,富美神社公演、富美地区住民センター、墓地の清掃と草刈りを行っている。 毎年楽しみの盆踊り大会は、8月16日に催し,子供盆踊り、仮装盆踊りがあり、住民のほとんどが踊りの輪に加わる。 富美神社祭典の10月10日は,地域の平和と作物の豊作を祈りながらカラオケ、踊り、児童の太鼓などによる演芸会を楽しむ。 自治会が管理しているものは、富美地区住民センター(町が委託)、営農飲雑用水施設、富美神社、神社公園、乳牛品評会場、花壇(老人クラブ)、墓地のほか史跡、碑、保全樹木の原始木などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 辻正夫(昭和33年~同50年)、村田憲夫(同51年~同53年)、成瀬徳雄(同54年~同59年)、斉藤昭三(昭和60年~平成3年)、長倉義勝(同4年~現在) 【町議会議員】 辻正夫、斉藤昭三、成瀬徳雄、高谷紀雄 【農業委員】 岩崎樫三郎、竹内孝一、木村新市 【農協理事】 長倉義勝、吉田農夫雄 【農協監事】 村田豊彦、斉藤昭三、村田耕一 【農事部長】 長倉義勝、成瀬徳雄、斉藤昭三、松田剛、村田耕一、竹内一徳、緑川光雄 【農協婦人部支部長】 成瀬キクイ、村田梢、斉藤むら、三沢ヒフミ、本多キサ、関口美子、長倉キミ子、松田清子、小畠文子、村田礼子、伊藤藤子、片平悦子 【富美老人クラブ会長】 青柳盛、武田万,三井甚五郎、村田利雄、竹内孝一、片平正雄 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14節 | 上富美自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち まだ富美地区に含まれていた当時の明治42年(1909)ごろ、現在の上富美入口付近に武田三郎が入地した。 それをきっかけに、その後、奥地への入地もみられ、大正2年(1913)には7戸になった。 さらに、滋賀団体の入植と多田農場や山中農場開設があり、同7年(1918)には40戸に達した。 このため同9年(1920)7月、上富美が富美から分離独立した。 開拓当社は薄荷生産が主であったが,地力が衰えると麦類の生産が中心となった。 しかし、昭和10年代(1935~)から酪農が次第に盛んになり、これが発展して現在に引き継がれている。 戸数は、大正13年(1924)の74戸をピークに下降線を描き,平成9年(1997)3月末の住民基本台帳では10戸に減り、人口もわずか39人となっている。 区域は,町内西部、湧別川左岸に一市、東と西北は富美に、東南は開盛に,南と南西は遠軽町に、そそて西は紋別市にそれぞれ隣接している。 上湧別市街から地区の中心まで約12㌔㍍離れている。 主な出来事 地域の過疎化で児童数が激減し,昭和61年(1986)に上富美小学校が閉校、富美小学校に吸収合併された。 酪農家に朗報となったのは昭和50年(1975)のバルククーラー導入である。 それまで牛乳は缶に入れて輸送していたが、これにより入室管理上の問題が解決し,乳牛多頭化飼養に拍車がかかった。 昭和59年(1984)6月末、共栄の沢道路(1325㍍)の改修工事が完了、交通の安全性が図られた。 また、翌60年(1985)に開盛~上富美間の町道も改修され、急カーブ、急坂が解消された。 自治会活動のよりどころとして昭和53年(1978)11月、国の補助事業により上富美農業センターが建設された。 それまでは各種会合に狭い集会場しか利用できなかったので、住民の喜びは大きかった。 大雨が降るたびに道路の冠水などの被害を及ぼしていた地域内の原始河川が,平成3年(1991)に改修され、その悩みも解決した。 自治会年表 (昭和50年以降)
自治会の活動 昭和41年(1966)に自治会が結成した上富美火防団は,自衛組織として消防活動だけでなく、その他の災害出動にも備えているが、同53年(1978)、それまでの威力のない消防ポンプに代わり、町、農業協同組合の助成を受けて森田式34馬力の新鋭消防ポンプを導入した。 上富美神社の例大祭は、毎年10月15日で、五穀豊穣、諸災鎮護を祈願、馬頭観世音の祭典は毎年8月16日に催し、家畜の厄除けを祈願している。 このほか電気利用組合を通じ上湧別町農業協同組合分収林において補植、下草刈り、間伐、除伐などを行い、7割分収の事業を進めている。 自治会が管理しているものは、上富美農業センター(町が委託)、バス待合所、上富美神社、馬頭観世音のほか、記念碑、史跡などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 諸橋誠一郎(昭和43年~同50年)、山中巌(同51年)、山口政行(同52年~同57年)、花木直治(昭和58年~平成5年)、今井哲也(同6年~現在) 【農業委員】 千葉敏男、三谷義明、山口政行、佐藤与作 【農協理事】 佐藤与作、千葉紘一 【農協監事】 山中巌 【農事部長】 山口政行、佐藤与作、山口正巳、近藤正司、今井哲也、鈴木光俊 【農協婦人部支部長】 諸橋てるの、千葉トキ子、山口久、佐藤豊子、花木ミエ子、千葉京子、今井さだ子 【上富美寿(老人)クラブ会長】 千葉敏男 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15節 | 札富美自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成り立ち その区域の一部に屯田兵村の第二給与地が配置されていたので、大正3年(1914)ごろには解隊後の屯田戸主やその家族を中心に7戸が入植していた。 同8年(1919)以降中島、安藤、小山永などの各農場が相次いで開設され,入植者が急増した。 同10年(1921)には、5の1から分離、札富美として独立した。 大正14年(1925)、15号線地先の湧別川に札富美橋が架設されると、交通の便が良くなったので翌15年(1926)には戸数が42戸に増えた。 大正の中ごろから昭和13年(1938)ごろまでは薄荷の黄金時代で,地域内の80%は薄荷畑であったが、その後幾多の変遷を経ながらも酪農が着実に盛んになり、現在に至っている。 区域は,18号線と湧別川の交点から18号線を西へ進み湧別町界に至り、旭・5の1・屯市・4の3の各自治会界とする一円であり、湧別川の西に位置する。 平成9年(1997)3月末の住民基本台帳では人口と戸数は、37人・8戸で、大幅に減少している。 主な出来事 昭和56年(1981)、道営草地整備改良事業により旧岡本川に明渠排水工事が実施され、草地整備が大きく進んだ。 翌昭和57年(1982)、札富美老人クラブが北海道花壇コンクールに参加し,見事に奨励賞を射止めた。 同クラブは、町の花いっぱい運動の花壇コンクールの常連で,平成8年(1996)までに最優秀賞9回、優秀賞7回の素晴らしい成績を収めている。 自治会年表(昭和50年以降)
自治会の活動 毎年5月と10月の2回、道路脇の空き缶拾いを,7月に農免道路の草刈りをそれぞれ自治会全戸の参加で実施している。 また、6月16日の馬頭観世音の供養、8月19日の老人クラブ主催のぼっこしゃくようも年中行事になっている。 自治会が管理しているものは、札富美会館、馬頭観世音などである。 歴代自治会長他 (昭和50年~平成9年) 【自治会長】 深見信之(昭和48年~同54年)、片岡隆雄(同55年~同62年)、深見信之(昭和63年~平成5年)、志鎌哲雄(同6年~現在) 【農業委員】 安藤国夫、熊谷時男 【農協理事】 安藤国夫 【農協監事】 安藤国夫(平成8年から代表監事) 【農事部長】 深見信之、片岡隆雄、志鎌哲雄、熊谷時男 【農協婦人部長】 福島よね子 【農協婦人部支部長】 福島よね子、菊地常子、志鎌孝子、安藤靖子、片岡由美子、深見静子、熊谷基美 【札富美老人クラブ会長】 斉藤一盛、片岡幹雄、安藤コト,片岡隆雄、深見信之 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||