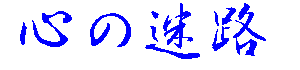「義姉のところへ行く途中でな。野暮用を足していたら日も暮れてしまい、日も暮れついでに、久しぶりに夢さんの顔が見たくなった」
そう言って、紫乃は愛用の扇をかざし、「うふふ」と笑った。
「よくここにいるのが判ったな」
不意の訪問に、嬉しそうに夢殿は客間に招き入れた。
「なんの。野暮用先で聞いたのよ。夢さんは毎年この時期には、軽井沢の別荘で一人籠もって、なにやら思案しているとな」
「おれだって、年に一度くらいは気分転換したいさ。ここには誰にも寄せ付けないし、家族もそれは承知のうえさ」
「お邪魔かぇ?」
「まさか。紫乃なら大歓迎だよ。いつでも。」
サイドボードから洋酒の入ったデカンタとグラスを二つ取り、紫乃と自分のグラスに琥珀色の液体をそそいだ。
「生憎、紫乃を満足させられる日本酒は、ここには置いてないからな。これで我慢してくれ」
「なんの。西洋の最高級酒ではないか。」
それから小一時間ばかり、お互いの近況報告のような話が続き、デカンタに新しい洋酒がつぎ足された。そんな夢殿の仕草を紫乃はぼんやりと眺めていた。
「おや」
サイドボードわきの暖炉のうえの写真立てで紫乃の視線が止まった。いくつか並んだ写真の中に、懐かしい持統院のものがあった。そしてその横には新吾の結婚式の写真。その隣に摩利の写真があった。
「懐かしいのう。あの小さかった新吾がもう結婚とは。」
「ああ。披露宴での紫乃の舞は見事だった。同席していた大臣が、帝国劇場のこけら落としに是非にと懇願していたくらいだ。断ったんだって?」
「夢さんの耳にまで入っていたとは。ゴタゴタが苦手での」
「持統院の同窓だと知って、遠回しに説得を頼まれたよ」
「おや。それで」
「遠回しに辞退した」
紫乃は満足そうにグラスの酒を飲み干した。
「新吾のために舞ったんだろ。」
「ふふ。新吾は念弟だからの。特別じゃわい」
「純情で友情に厚い新吾を何のダシに使ったんだい?」
「いろいろあってな。」
小さく息をつく紫乃に、夢殿はそれ以上は尋ねなかった。
「摩利の横に、新吾の婚礼の写真は酷ではないかえ?摩利がこれを見たら、あんたに文句のひとつは言いそうだ」
「そういう摩利を見るのも愉しみでね」
「まだ思い切れてはおらぬのかえ」
「ああ。底なし沼に落ちたようなものさ。」
「損な役まわりよの」
「なんの。俺はそれを愉しむ術を見つけたからね。」
「その余裕で、摩利の心に滑り込む魂胆だと?」
「鋭いね紫乃。そうかもしれない。心の中は新吾でいっぱいでも、心と体は別ものだからね。俺はそういう男の性を利用しているのさ。」
「同じ遂げられぬ想いを持っても、摩利には死んでも出来ぬことかもな。」
「正々堂々と正面から。それがあいつの良いとこさ。」
そう言いながら、夢殿は一気に杯を空けた。
「心底、惚れておるのだな。あんたはあんたで、死ぬまで想いを胸に抱いたまま、摩利ひとすじを想い続けるわけか」
「ロマンチストだねぇ、紫乃。そういうおまえも、胸に秘めた想いがあるんだろう」
「抜け目がないな、夢さんは」
「気づかないでか。何年の付き合いになると思ってるんだよ。俺は野心もあるし、今の地位も失いたくない。家族も大事だ。底なし沼に落ちても、這い上がってくるタイプの人間かもしれん。だが、摩利を失いたくない。底なし沼にいるのが摩利なら、何度でも落ちて、また這い上がるさ」
「強いな、夢さんは」
三度めにデカンタにそそがれた洋酒がなくなった頃、どちらともなく、客間のソファで寝入ってしまい、夢殿が目を覚ましたのは深夜遅くになっていた。
わずかに開けていた窓から、ひんやりとした避暑地の風が部屋のなかにそよいでいた。何時頃寝てしまったのか、天窓から入る月の光だけが明かりだった。
向かいのソファに寝ている人影が、ぼんやりと夢殿の視界に入ってきた。
「風邪ひくぞ、摩利」
そう言いかけて、寝ているのが摩利ではなく紫乃で、深酒をしているうちに寝入ってしまったことを思い出した。
そうだった。紫乃が来て、久しぶりに持統院の話をして。以前、摩利が帰国したときに、軽井沢の別荘まで訪ねてきて、それからこの時期になると、一人の時でもここに来てぼんやりと過ごすことが習慣となっていた。
十代の頃と違い、摩利はもう決して人前で崩れたりせず、自らの叶わぬ恋を浄化させていた。
「あれから修行と経験を積みましたからね」
そういって笑いながら摩利は夢殿の前にいた。成就しない恋に焦がれる想いが、彼の美しさをいっそう際だたせているようだった。
酔ったふりをして唇を重ねても抵抗せず、やさしく返してくる。
「いささか戦意喪失だな」
「どうしてです?おれは夢殿さんが好きですよ。」
「二番目・・・にだろ」
「そういうところが好きですね」
「おまえが女でなくて良かったよ」
「いつの間にか寝てしまったらしいのう、夢さん」
紫乃の声で、夢殿は、はっとして我に返った。
「ああ、そうらしいな。」
「よい酒は悪酔いせぬな。なんとなく心地よい。ぼんやりと、何を考えていた?」
「前に、摩利がここへ来たときのことを思い出していた」
紫乃は黙ったまま聞いていた。
「心の片隅じゃ、全然決着していないのに、表面では波風ひとつ立っていなかった。たいした奴だよ。あいつが、女でなくて良かったと、そう思っていたところさ。あいつがもし女だったら、おれは人生を狂わせていたかもしれん。」
「苦しんでこそ、恋は本望なのかもしれぬて。夢さん。皆、そんな迷路の中を出口を求めて探し続ける一生かもしれぬのう」
夜の闇がお互いの表情を隠し、やわらかな月の光が、お互いの姿だけを照らし、大正十二年八月三十一日に日付が変わってた。