誰も知らない
こんなこと言っても、誰も信じちゃくれないでしょうが、カンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞する前から、この作品は観ようと思っていました。
理由は、作品自体にオタク度を感じたから。
物語的には、「お涙頂戴」要素が強く感じられる題材ですが、初めて予告らしき映像を見た限りでは、安っぽい浪花節調感動強要が無かったわけです。
私が観たのは札幌市内のシアター・キノ。映画ファンに愛されている小さな映画館です。何度か行ったことはありますが、超満席で補助椅子が出たのを見るのは初めてでした。
物語はテレビ等で宣伝されているとおり、子育てを途中放棄してしまった母親に置き去りにされた子供達の、約半年に渡る生活を描いた内容です。
母親の人間性とか、子供だけで暮らしている実態を傍観した社会性とか、そういった「見所」を作るわけでもなく、ひたすら淡々と特殊な日常が、あたかも自然のようにスクリーン上で流れていくのです。
どこまでが演技なのか、線引きが出来ないような4人の子供達。彼らはきっと、母親が大好きで、母親だけが生活であり生きるための原点であるように思う。
母親役は個性的なYOUさんなのですが、これが絶妙なキャスティング。重く演じていないため、深刻なはずの話がドロドロしない。
誰がみても、とんでもない母親なのだが、家にいる間は子供を彼女なりに愛しているし、子供も幸せなのだ。しかし、一歩外に出ると子供のことはケロッと忘れ、本能のままに生きてしまう。母性が欠落した母親なのかもしれない。
そんな母親を愛し、待ち続ける4人の子供。
母親の言いつけを守って4人で暮らせば、母親が戻ってきてまた楽しく暮らせるという思考が、いつの間にか植え付けられているように感じられる。
表面の、一番薄い部分だけ世間と繋がっているだけで、不思議と展開していく子供だけでの暮らし。
電気や水道、ガスが止められても、誰も調べには来ない。そういうことへの異議提議を唱えるための作品でもない。ただひたすら、社会の片隅で生きている子供達の姿を追うだけの話でしかない。
感動や同情を求められもせず、単調に流れる「時」。
まるでドキュメンタリーを観ているような子供達の姿には、同情を誘うような場面は一切ない。だからこそ、悲劇性が薄く、むしろ透明感すら感じられる仕上がりになっていた。
母性を一部欠落している母親と、母親を慕う子供。野生動物にも稀にみられる事例だけれど、どんな動物であってもそれは悲劇でしかない。
戸籍すら持てなかった子供達の将来を含めて考えるのも、単に「可愛そうだった」と涙して終えるのも、どういう感想を持つのもご自由に、という作品だったように思う。
劇場には、子供を慈しんで育てたのであろう年配の観客が圧倒的に多かったが、親の愛情を受けながら育てられている年代にこそ、観て欲しい作品かもしれない。
我が子を育てられないと思うのなら産まない。しかし、少子化問題が深刻だから産めと政府が提唱するなら、責任をもって国で育てる。そういった問題をキチンとしないで、出産だけを奨励すると、悲劇はこれからも続くのかもしれない。
最後に、カンヌで受賞したのは柳楽クンだけですが、4人全員が素晴らしかったです。あれは4人とYOUさんへの賞だと私は思ってます。
モーリス・ベジャール/ルミエール
世界的な振付家、ベジャールの新作「ルミエール」が出来るまでのドキュメンタリー映画。
実際のダンス場面は思ったより少なく、気むずかしいベジャヘール氏の様子がビシバシ伝わりました(笑)。
お隣席の老婦人は熟睡してましたねぇ。そうだよねぇ〜、だってなんの事件も山場も無いんだもん。
ワタシ的な見所は、そうですねぇ、小林十市くんの男とのキスシーンでしょうか。あれって、「ルミエール」の一コマなのかしら・・・気になる。
ベジャールのファン、若しくはバレエが特別に好きというわけでもなかったら、あまりオススメでもないような・・・・・。
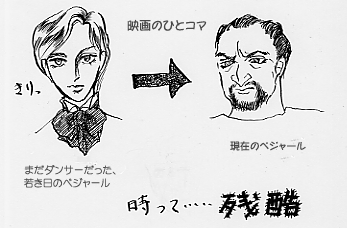
![]()